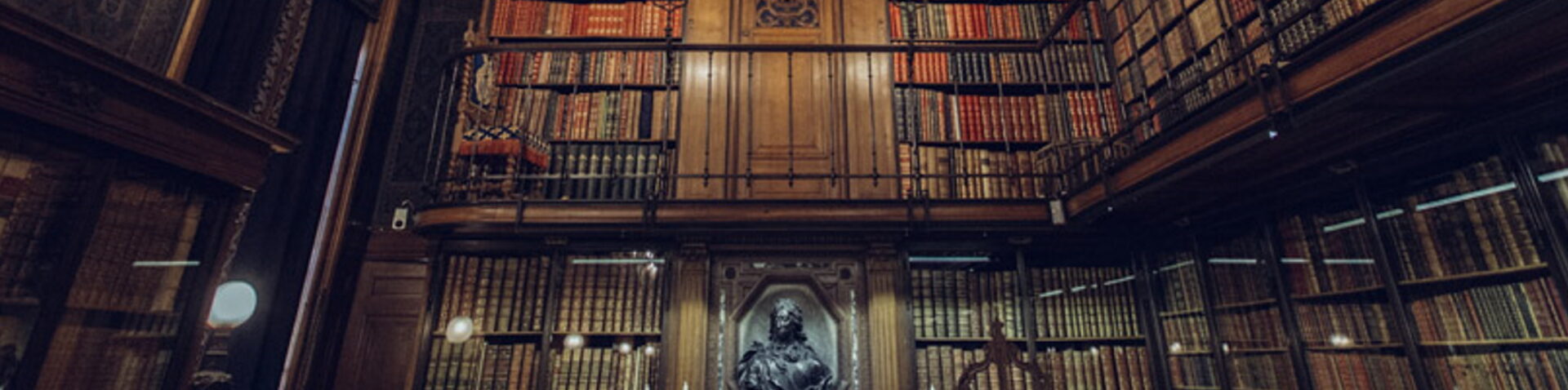□ 椎野先生との往復書簡(第2回) クルーズ船寄港、地域を潤す 裕福層30万円 周辺ツアー、昨年2479回、9地点で最多
椎野 潤 (しいの じゅん)
「巻頭の一言」
日本各地の港で大型クルーズ船の寄港が活発になっています。新型コロナウイルス禍で一時激減しましたが、国土交通省がまとめた2024年の国内寄港回数(速報値)では、2479回と過去最多(2930回)だった2018年の85%に回復し、9地点で最多を更新しました。大型船向けに港を改良し官民で誘致した静岡市の清水港などは寄港急増が街を潤しています。2025年6月21日、日経朝刊、2面記事、(鈴木泰介、浜野琴星)を参照・引用して記述。
「日本再生]「地域創生」「クルーズ船寄港、地域を潤す」裕福層30万円 周辺ツアー、昨年2479回、9地点で最多。
「はじめに」
都道府県別に2018年と比べた寄港回数の増減数を集計したところでは、増えたのは15都道府県でした。静岡県が58回増と最も増えて、過去最多の91回になりました。北海道が29回増、大阪府の27回増がこれに続きました。
日本発着のクルーズ船の場合、10日間ほどで国内中心に韓国など東南アジアの港と合わせ10か所前後を巡り、料金は船や部屋の種類により、20万~100万円を超すプランもあり、インバウンド(注1)の富裕層も多く乗船します。
乗客は船内で充実した食事を楽しみ、寄港地ではその土地ならではの体験や特産品に期待します。迎える側もコト消費や土産物に重点を置いています。
[静岡県清水港]
静岡県清水港の日の出埠頭に5月25日、「セレフリティ・ミレニアム」「ノールウェージャン・スピリット」の2艘が並びました。港の改良工事で2024年3月に15万トン級の同時接岸が可能になって初めての大型クルーズ船2艘同時寄港となりました。
乗客は約4000人。停泊する8~10時間を使い、乗客らは無料シャトルバスやタクシー、徒歩で出かけ、港周辺の街は、にぎわいを見せました。
清水駅前銀座商店街は静岡市と有志が乗客向け街歩きツアーを開催しました。呉服店で着物を紹介し、刃物店で包丁研ぎを実演しました。だしの試飲会をした次郎長屋には、街歩き後に再び訪れて買っていく乗客もいました。
清水港からは、50キロほど離れた身延山久遠寺(山梨県身延町)や茶摘み・茶道体験ができる「ふじのくに茶の都ミュージアム」(静岡県島田市)に車で向うツアーもありました。代金は1人10万円を超します。
乗客の中には総額30万円近いツアーを個人で手配して回った富裕層もいました。10万円超の着物の生地や数万円の刃物など高額品を買う人も増えたのです。
静岡県によりますとクルーズ船寄港が地元にもたらす経済効果は1艘あたり約2140万円と試算され、単純計算で2024年の県内の経済波及効果は、約19億円、2018年に比べ12億円ほど増加したと推計されています。
清水港は晴れた日なら港に向う船から世界遺産の富士山を一望できます。東京や横浜から近く、欧米の船会社からの人気は高いのです。静岡県・市と民間からなる「清水港客船誘致委員会」も積極的に誘致し、歓迎セレモニーなどで港の評価を高めました。2024年の寄港は87回で、2025年は約110回と最多更新を見込んでいます。
[北海道小樽市]
北海道小樽市の小樽港は船が港に1泊し、乗客が寄港地で夜の観光を楽しめるオーバーナイトステイ(注2)の誘致に力を入れています。2025年に寄港が予定される32回のうち8回は1泊以上となる見通しです。
「バイキング・オリオン」が5月に1泊した際は、港の施設内に午後9時半まで臨時の観光案内所を設け、すし店などに送客しました。人気の高い小樽運河では2022年から秋に飲食店や雑貨店が並ぶナイトマーケットを開催しています。
[この項のおわりに]
クルーズ船観光に詳しいJTB総合研究所の亀山秀一主席研究員は「船会社は寄港地ならではの体験を提供したい。寄港地側は誘致や消費拡大のため、そこにしかない体験や特産品だと外国人に説明する力が求められているのです」と話しています。(鈴木泰介、浜野琴星)
[まとめ]
この研究報告の執筆で参照・引用した、日本経済新聞の2025年6月21日朝刊2面記事に、三つの図表が記載されていた。①「クルーズ船寄港回数の増減」港湾関係者からの聞き取りを基に、国土交通省港湾局が港湾別に集計。②「実回数では沖縄県が最多。」➂「国内全体でコロナ禍からの回復が進む。」(注)2024年は速報値。出所は国土交通省。
[図表1]
図表1(注3)は、2025年6月21日の日経新聞紙上に、日本列島の地図として記載されていました。この図表は「クルーズ船寄港回数の増減(2018-2024年)」と題した図表でした。そして、この「寄港回数の増減」を6段階の群に分けて整理し、これを日本列島の地図の上に、青色系の色彩で塗り分けて記述していました。これは以下です。
第1群「クルーズ船寄港回数の増減」が10回以上増加したところ(黒色)。
第2群「クルーズ船寄港回数の増減」が1~9回増加したところ(黒色の右斜線)。
第3群「クルーズ船寄港回数の増減」が0~10回減少したところ(濃い青色)。
第4群「クルーズ船寄港回数の増減」が11~50回減少したところ(淡い青色の左斜線)。
第5群「クルーズ船寄港回数の増減」が50回以上減少したところ(淡い青色)。
第6群「クルーズ船受け入れ港なし」(灰色)。
次に、この第1群から第6群の各地域について述べます。
[第1群]
ここでは「クルーズ船寄港回数が10回以上増加したところ」を第1群とよびます。第1群に入っていたのは以下の地域です。その第1群の第1位は、静岡県でした。また第2位は北海道、第3位は大阪府、続いて東京都と高知県が続きました。第1群に入っていたのはこの5ヶ所です。
第1位の静岡県では、清水港が代表的な港です。清水港では改良工事が完了し、15万トン級の大型客船が2艘同時に停泊できるようになりました。これで街は大変なにぎわいを現出することになったのです。
フェリーで来る来客は4000人です。この大勢の客が、停泊する10時間を一杯に使って、無料シャトルバス、タクシー、徒歩で街に乗り出しました。街は客で溢れました。北海道各地も大阪も大賑わいです。東京都、高知県も第1群に入っていました。でも、東京・高知については、今回の記事では、具体的な活動の記述はありませんでした。
[第2群]
第2群は「クルーズ船の寄港回数が0~9回のところで、黒色の右斜線で示した地域で
した。これは以下です。青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、愛知県、大分県、宮崎県、徳島県の10県でした。
この2群を眺めてみますと、東北地方が勢揃いしているのに驚かされます。青森、岩手、秋田、山形、福島が並んでおり、隣接の茨城も加えて6県も集まっています。その他はトヨタのいる愛知、九州の大分・宮崎、四国の徳島がここに入っていました。
[第3群]
このプロジェクトの6群の内、クルーズ入港が増えていたのは第1群と第2群だけで、
第3群からは減少組となります。この第3群は、「クルーズ船の寄港回数が0~10回減少したところ」です。これは濃い青色で示した地域です。それは以下です。宮城県、新潟県、富山県、石川県、鳥取県、島根県、千葉県、和歌山県、佐賀県、熊本県、鹿児島県の11県でした。ここは減少を最少に止めて頑張っている地域です。
[第4群]
第4群は、「クルーズ船の寄港回数が11~50回減少したところ」です。これは淡い青色で示した地域でした。ここはこのプロジェクトで、立ちおくれた2地域の内の1地域です。
ここにいるのは、神奈川県、京都府、三重県、兵庫県、岡山県、山口県、愛媛県、香川県の8地域でした。そうそうたるメンバーが、この群に止まっていました。でも、まもなく元気な活動が始まると予測しています。
[第5群]
第5群は、「クルーズ船の寄港回数が51回以上減少したところ」で、淡い青色で示した地域です。ここにいるのは以下です、広島県、福岡県、長崎県、沖縄県です。ここは減少量が最大になったところです。ここには、過去に、全国のブロジェクトを牽引した地域が、ずらりと並んでいたのです。でも、一つ弾みがつけば、一気に上昇してくるでしょう。
[第6群]
第6群は、「受け入れ港なし」の地域です。「灰色」で示しています。これは、日本列島の中央部で、海に接していない地域です。これは以下です。栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県の8か所です。
[図表2]
図表2(注4)は、「実回数では沖縄県が最多」と題した図表でした。これは日本経済新聞の2025年6月21日の朝刊に掲載されていた図表です。これは以下の表です。
図表2 実回数では沖縄県が最多
都道府県 寄港回数 主な地域 図表1船寄港回数の群
1位 沖縄県 386回 那覇、石垣 第5群
2位 長崎県 248 長崎、佐世保 第5群
3位 広島県 222 ヘラビスタマリーナ、広島 第5群
4位 福岡県 216 博多、北九州 第5群
5位 鹿児島県 151 鹿児島 第3群
6位 神奈川県 147 横浜 第4群
7位 北海道 131 函館、小樽 第1群
8位 兵庫県 104 神戸 第4群
9位 静岡県 91 清水 第1群
10位 東京都 81 東京 第1群
私は、この図表2で記した内容と、図表1で分析した「クルーズ船の寄港回数の群」とを照らし合わせたいと思い、これを図表2に付記しました。その結果、私は大変に驚きました。この図表の第1位から第4位までの都道府県が、図表1の「クルーズ船寄港回数の群」では、第1群ではなく第5群(成績最下位)になったからです。この図表2の図表名では、「実回数では、沖縄県が最多」と記してありました。でも、この図表2において「沖縄に続いて長崎、広島、福岡が続きます」と言って良いのでしょうか。私は、どうも納得がいかなかったのです。
図表1の「クルーズ船の寄港回数(2018年-2024年)」では、沖縄県、長崎県、広島県、福岡県は、51回以上の減(青色、成績最下位)の群で表示されています。すなわち、この4県は、2024年での成績は悪いのです。でも、図表2での沖縄、長崎、広島、福岡の寄港回数の386、248、222、216回は、成績好調です。2025年は快調に転じたと思われます。
図表2では、実回数の沖縄県をトッブに記し、続いて長崎、広島、福岡の順に書いてあります。そして、図表2には、このデータの時期の明記がないのです。図表2には「2025年の推測値データ」との注記はないのですが、これを記載もれと考えると、大分、様子が変わるのです。ここでは2025年についての記述が必要なのです。
もし仮に、図表2に「2025年現在の推測値」と付記し、次の図表3の「国内全体でコロナ禍からの回復が進む」も、2024年の棒グラフの次に2025年の棒グラフを置き、(2025年の現時点での推測値)と記して並べてみれば、これは、すっきりと分かるのです。こうすると図表3の2025年現時点での推測値は、2024年より、かなり高い棒グラフになると思います。
でも一方で、静岡県については、2025年の年間訪問回数を110回と前半の解説で述べていますから、図表2の寄港回数91は、数値が小さくて合致しないのです。
このように考えると、この図表1での第1~6群の群分けも、これは2024年のデータですから、2025年のデータに差し替えしなければならないのです。そうなると図表2も全面書き直しになります。いろいろ、根本的に解決しなければならない課題が、夥しく出てくるのです。
私は、この図表2は、読者の便を考えて、最新の未公開データを、追加で示してくれたものだと思います。いずれ、正しい数値が公表されるはずです。
[図表3]
図表3(注5)は、「国全体でコロナ禍からの回復が進む」と題した図表でした。これは日本経済新聞の2025年6月21日の朝刊に掲載されていた図表です。これは以下の通りです。
この図表の左側縦欄には、0、500、1000、1500、2000、2500、3000回の、寄港回数が列記されており、また、横欄の下欄には2015年、17、19、21、2024年の(年)が記してありました。
ここでは、この縦欄と横欄を用いて、「クルーズ船寄港回数」の年別の棒グラフが書いてありました。このグラフは、以下のことを示しています。2015年の1500回からスタートし、2019年には3000回にまで至りました。その後、2020年のコロナ禍で打撃を受け、250回にまで転落しました。そして2022年まで少しずつ回復し、2024年には2500回にまで回復したのです。
すなわち、「クルーズ船の寄港回数」は、コロナ禍の大きな打撃を乗り越えて、2024年には、過去最大だった2018年の85%にまでに回復したのです。
[おわりに]
この論文は、結局、廃棄されることになりました。「この国の行き先は、何処にいくのか」と言うことを問い続け、二転三転し、その結果、今の段階での一つの結論に達した、この研究は、きわめて重要です。それで、この未完成論文を、あえて発表して、皆様に公表しておきます。
(注1)インバウンドとは、外国からの訪問者が、日本に訪れて行う観光やビジネスの動きを意味する語である。2024年の外国人訪日客数は3億3686万9000人に達し、過去最高を記録した。インバウンド消費額も過去最高の9兆1295億円を記録し、インバウンド市場は伸び続けている。
(注2) オーバーナイトステイ。ホテル業界における「オーバーナイトステイ」とは、宿泊が1泊限りの滞在を指す用語ある。
(注3)日本経済新聞2025年6月21日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。図表1①クルーズ船寄港回数の増減(2018年-2024年)。通関関係者からの聞き取りをもとに、
国土交通省港湾局が港湾別に集計。
(注4)日本経済新聞2025年6月21日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。図表2②実回数では沖縄県が最多。
(注5)日本経済新聞2025年6月21日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。図表3
➂国内全体でコロナ禍からの回復が進む。(注)2024年は速報値。出所は国土交通省。
(1) 日本経済新聞、2025年6月21日、朝刊(2面)。
[付記]2025年7月14日。