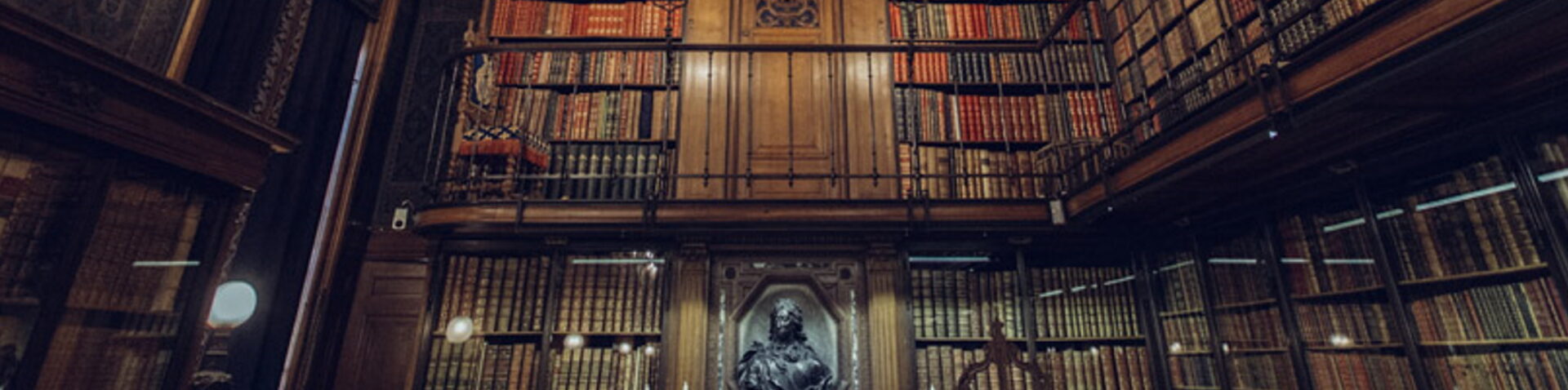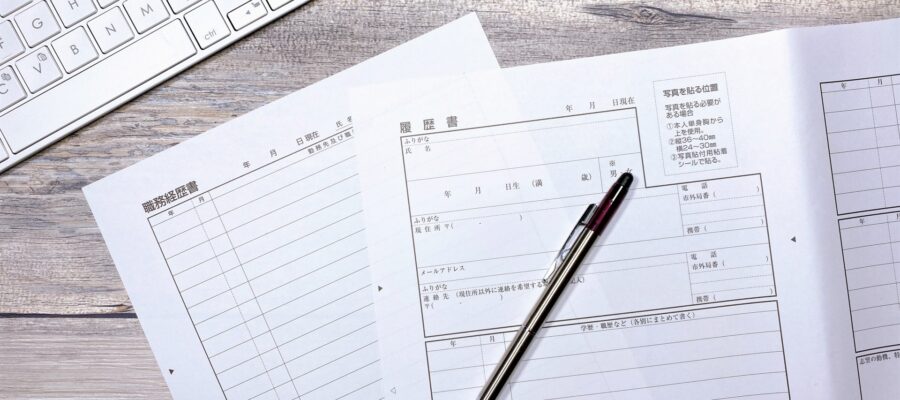椎野 潤(しいの じゅん) 2025年10(研究報告№153)
「巻頭の一言」
自治体が運営する無料の職業紹介所「地方版ハローワーク(注1)」が、群れる働き手を発掘しています。2025年5月時点で、全国に992か所あり、島根県は県と全19市町村が設置しています。地域課題を解決する自治体の政策と連動した職業紹介で、働く意欲のある高齢者や女性、障害者らの背中を押します。就職率は2019年度以降、国のハローワーク(注2)を上回ります。
地方版ハローワークは、地場産業の振興や介護・福祉の人出不足解消、移住促進といった地域課題を解消する政策の効果を高めるため、自治体が独自に職業紹介を実施しています。
地域のニーズを、きめ細かく吸い上げて雇用に結びつけ、2023年度の就職率は全国で31.3%になり、民間の職業紹介は存在感を増し、就職件数の減少が続く国のハローワーク(注2)の26.8%より、4.5ポイント高くなっているのです。
都道府県別に自治体の設置割合をみると、島根県が100%で最も高く、鹿児島県の66.9%、大阪府の61、4%が、これに続いています。現在、ここまで進んでいます。
日本経済新聞2025年8月23日、朝刊2面記事(若杉敏也)を参照・引用します。
「日本再生][地域創生] 地方版ハローワーク浸透 希望聞き取り 雇用側とも交渉 全国990ヶ所、島根県は全市町村
「はじめに」
地方版ハローワークは、地場産業の振興や介護・人出不足解消、移住促進といった地域課題を解決するため、自治体が独自に職業紹介を実施しています。
地域のニーズを、きめ細かく吸い上げて雇用に結びつけ、2023年度の就職率は全国で31.3%でした。民間の就職紹介が存在感を増し、就職件数の減少が続く国のハローワーク(22.6%)より4.5ポイント高くなっているのです。
都道府県別に自治体の設置割合をみますと、島根県が100%で最も高く、鹿児島県の65.9%、大阪府の61.4%が続きます。
[島根県・益田市]
島根県益田市は、介護保険の課題解決を目指し、地方版ハローワーク(注1)を活用して高齢者福祉課が実施する入門研修や、UIターン人材への働きかけと平行して課内に設置した「無料職業紹介所」が、介護の周辺業務の求人と求職者のマッチングを開始したのです。
施設の部屋の清掃や食事の片付け、利用者の話し相手など、資格が不要な周辺業務を担う人を多数確保することで、資格がある職員が食事や入浴の介助、専門的知識が必要な業務に集中できるようにするのが狙いなのです。
経験や年齢、勤務時間、資格の制限を設けず「介護お助け隊(注3)」として募集したところ、4年間で延べ97人が登録し、43人が職を得ました。2024年度の就職率は50%でした。
益田市は、広報紙やチラシのほか、介護保険や家族の看護相談で、市役所を訪れた高齢者らに地方版ハローワーク(注1)を紹介して周知してきました。「普段から足を運ぶ市役所の窓口に、これを開設したことで、動きたくても一歩も踏み出せなかった高齢者のニーズを掘り起こせたのです」と益田市の高齢者福祉課は言っています。
就職を支援する部署がなかった島根県立農林大学校には、県が地方版ハローワークの「無料職業紹介所」を開設しました。この結果、2024年度の就職率は72.7%に達しました。
[鹿児島県日置市]
子育て支援所帯の転入が増える鹿児島県日置市では、ハローワークを、主に、保育の人材確保に活用しています。子育て支援や保育所を担当する「こども未来課」に地方版ハローワーク「保育のおしごと支援センター」を設置したのです。
職種は保育士や看護師、調理員、送迎バスの運転手などです。専任のコーディネーターが、就職希望者と対面で、希望を詳しく聞き取って、保育の現場見学や面接日程を調整するのです。2024年度の就職率は、女性を中心に40%で就職後のサポートも続けています。
2人目の子が1歳なったのを機に再就職先を探しはじめた日置市の女性(33)は、2024年7月、センターが市役所を仲介し市内の民間保育園で常勤保育士として働き始めました。当初の求人は非常勤だったのですが、幼稚園教諭をしていた経歴を踏まえ、センターが園側と交渉し、採用条件の変更を実現しました。
[まとめ]
中央大学の阿部正浩教授は、地方版ハローワークについて「地域課題のニーズをくみ取る自治体の施策に合わせた活用は、効果が期待される」と評価しています。
そのうえで「高齢者や女性の就職支援は、国のハローワークも力を入れ、人材を奪い合う構図もある。地方版の一部は、開店休業なのです。地域の事情を詳しく知る強みを、マッチングに生かすことが、地域版でさらに求められる」と話しています。
[図表1]
2025年8月23日の日経新聞紙上に、2025年5月時点の地方版ハローワークの開設自治体割合を示す図表が記してありました。これを図表1(注4)としました。
この地図に示された地域は、4群で構成されています。次にこの4群を整理しておきます。
(1) 第1群、地方版ハローワークの開設自治体割合が50~100%のところ。
(2) 第2群、地方版ハローワークの開設自治体割合が30~50%未満のところ。
(3) 第3群、地方版ハローワークの開設自治体割合が20~30%未満のところ。
(4) 第4群、地方版ハローワークの開設自治体割合が30%未満のところ。
次に、この第1~4群の内容について述べます。
[第1群]
ここで第1群は、地方版ハローワークの開設自治体割合が50~100%のところです。
この比率を都道府県別にみますと、島根県は、県と全19市町村が設置しており、設置割合100%で、全国でダントツトップでした。次いで鹿児島県65.9%、大阪府61.4%が続き、以下鳥取県、岡山県、広島県、大分県、高知県が続いていました。この8か所が第1群でした。
[第2群]
第2群は、開設自治体割合が30~50%未満のところです。それを都道府県別にみますと、これは9か所ありました。それは以下です。秋田県、長野県、富山県、愛知県、滋賀県、三重県、兵庫県、愛媛県、香川県の9か所でした。これを濃い紫色の右斜線で塗り分けました。第2群はこの9か所でした。
この第1群と第2群の17ヶ所は、地域が偏在していました。本州の中央部の長野県から西と九州・四国に偏っているのです。その他は東北の秋田が1か所あるだけです。
[第3群]
第3群は開設自治体割合が20~30%のところです。ここは10か所です。これは以下です。北海道、福島県、群馬県、神奈川県、千葉県、福井県、京都府、山口県、宮崎県、沖縄県の10か所です。
[第4群]
第4群は、開設自治体割合が20%未満のところです。ここは開設自治体割合は最小のところですが、数としては、ここが一番多いのです。ここには20か所入っていました。
ここに入っていたのは以下です。青森県、岩手県、宮城県、山形県、新潟県、栃木県、茨城県、埼玉選、東京都、山梨県、静岡県、石川県、岐阜県、奈良県、和歌山県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、徳島県の20か所でした。
この「ビリ」に群れをなしている第4群は、大別すると4群があります。①東京を中心とする関東地方(6ヶ所、東京・栃木・埼玉・山梨・静岡・茨城)。②青森から新潟までの東北地方(5か所、青森・岩手・宮城・山形・新潟)。➂関西(4ヶ所、奈良・岐阜・石川・和歌山)。④九州(4か所、福岡・佐賀・長崎・熊本)。⑤四国(1か所、徳島)。
ここで、日本の3大都市は、劇的な別れとなりました。大阪は第1群で頑張っていますが、東京は「ビリ」の第3群に沈んでいます。京都は中間です。好調の大阪と最下位の東京のどこが違うのでしょうか。ここを真剣に考えねばなりません。
[図表2]
図表2(注5)は、「地方版ハローワークの開設は北海道が最多」と題した図表でした。これは日本経済新聞の2025年8月23日の朝刊に掲載されていた図表でした。これは以下です。
この図表2では、地方版ハローワークの開設数の多い都道府県について、その多い順に、第1位から第10位までを記載していました。
図表2 地方版ハローワークの開設は北海道が最多
開設ベストテン順位 都道府県名 地方版ハローワーク数
1位 北海道 111ヶ所
2 大阪府 99
3 長野県 51
4 兵庫県 42
5 神奈川県 41
6 鹿児島県 40
7 高知県 38
8 京都府 35
9 島根県 32
10 熊本県 25
都道府県平均 21.1ヶ所
図表2(注5)には、地方版ハローワークの開設数の多い順に、都道府県名を記し、あわせて、その「地方版ハローワーク数」を記してあります。
この図表2を見てみますと、地方版ハローワークの開設数が、最も多いのは、北海道の111ヶ所であり、第2位は大阪の99ヶ所で、この2か所が他を圧していました。第3位は長野県の51ヶ所で、第2位と第3位の間に差がありました。この後は、4位兵庫県の42ヶ所から第10位の熊本県の25ヶ所まで、順に列記してありました。
[図表3]
図表3(注6)は、「地方版ハローワークの就職率は30%以上は国を上回る」と題した図表でした。
この図表3の左欄縦欄に、20、25、30、35%と、国と地方版ハローワークの就職率(%)が記してありました。また、下欄横欄に、2012年、15、20、24年度と年度が書いてありました。
この「年度」と「国と地方版のハローワークの就職率」を用いて、「国と地方版」の「各年度のハローワークの就職率」の折れ線グラフが書いてありました。
この折れ線グラフを見た結果、以下のことがわかりました。
国のハローワークの就職率は、2013年度から2017年度までは、34%の高い就職率を維持していましたが、2017年度に、その低下が始まり、2019年度には、26%にまで激しく転落しました。そして2024年まで、その状況が続きました。
一方、地方版ハローワーク就職率では、2021年度の21%から2019年度の34%まで、途中の一時下落はありましたが、全体としては右肩上がりで上昇し、2019年度には、国のハローワーク就職率を上回りました。2019年度には、地方版ハローワーク就職率も急落しましたが、28%の低下で踏み止まり、2020年度からは、逆転の急上昇となり、2023年度まで32%を維持しました。2020年度~2024年度の間は、地方版ハローワーク就職率は、国のフローワーク就職率より上位を維持しています。
[まとめ]
自治体を運営する無料の職業紹介所「地域版ハローワーク」が、全国に1000以上設
置され、多くの働き手を再開発しています。これは、老衰化し始めている、日本の国家・社会・産業を、強力に立て直す活動のリーダーです。
この先頭に立つのが島根県で、ここでは県と県内の全市町村、19市町村に、「地方版ハローワーク」が設置されており、県内一致での取組みが開始されています。これにより、仕事を探し、働く人を増やして、島根県内各地の活性化は格段と進展しました。この先導者としての島根県に次いで、鹿児島県と大阪府が続いています。
この活動の先導者である島根、鹿児島、大阪の「地域版ハローワーク」の開設率は60%以上です。さらに50~60%で、続いている処が5ヶ所もあります。これは鳥取県、岡山県、広島県、大分県、高知県です。
でも、この各地での活動状況は、先頭牽引者の島根県を除いて、どこも、まだ、あまり公表されていません。
先頭の島根を追って、各地は大いに頑張ってくれていると思っていますが、私は、その具体的な活動の様子を、まだ、ほとんど知らないのです。私は、この各県の人達に直接連絡をとって、大いに激励し、その背中を強く押したいと考えています。でも、まだ、その機会を得ていないのです。
そこで、このブログを閉じるに当たって、この第一群の人達と連絡を取って、各地の「地域版ハローワーク」の現状とこれからの見通しを聞いてみようと思いたちました。それで、これまで毎日書き続けているブログを読み直して、連絡できる人の住所やメールアドレスを調べられないか、チャレンジを初めたのです。その結果は以下です。
日本の産業と企業の望ましい姿を目指して、現在、日本国中で熱心に進められている「地域版ハローワーク」の開発推進は、これからの日本の産業・社会の進化にとって、極めて重要な活動です。
私は、これを積極的に応援する活動の第1弾として、最近の6月から9月のブログを読み直し、これから鹿児島から高知に至る地域に関する記述があるものを選び出しました。この結果、見付けたのが、次に示す図表4の6つのブログです。それは以下です。
図表4 鹿児島・大阪・高知県・鹿児島・岩手・島根・鳥取県のブログ
発信年月日 県の名称 ブログの名称
① 2025年6月30日 高知県 転職人材、地方で優遇、求人の賃金 高知16%
増、企業改革へ管理職Uターン
➁ 2025年7月14日 鹿児島県 ゼブラ企業、社会貢献競う、鹿児島が最多EC代行、成長と両立、 全国1.7万
➂ 2025年7月28日 岩手県 地場産業を支える若き匠、岩手ファンクラブで大工育成、技能五輪入賞、地方が6割
④ 2025年8月25日 島根県 移住誘うマルチワーク、島根県、夏は稲作、冬は酒蔵、人口急減、123組合が雇用し派遣
⑤ 2025年9月22日 鳥取県 日韓自治体が協力で突破、鳥取県、IT導入や人口減対策
⑥ 2025年10月13日 島根県 地方版ハローワーク浸透、希望聞き取り、県は
全市町村
この6本のブログの第1群に入っている該当都道府県を拾い出してみると、それは以下でした。
(1) 9月22日のブログ(注11):鳥取県、神奈川県、北海道。
(2) 8月25日のブログ(注10):鳥取県、鹿児島県、福島県、北海道、新潟県、熊本県、宮崎県。
(3) 7月28日のブログ(注9): 茨城県、愛知県。
(4) 7月14日のブログ (注8) : 鹿児島県、宮崎県、和歌山県、大阪府。
(5) 6月30日のブログ (注7) : 沖縄県、高知県、東京都。
これを集計すると以下です。鹿児島県(3)、鳥取県(3)、北海道(2)、新潟県(2)熊本県(2)、宮崎県(2)、沖縄県(1)、高知県(1)、東京都(1)、和歌山県(1)、大阪府(1)、茨城県(1)、愛知県(1)、福島県(1)、神奈川県(1)。(注)( )内は、参照ブログ数。
すなわち、鹿児島、大阪、鳥取、北海道、新潟、熊本、宮崎、沖縄、東京、和歌山、茨城、愛知、福島、神奈川については、人材を探す地域の中に、是非とも、含めておく必要があるのです。
この参照ブログでは、どのブログも、大変有益なことが書いてあり、今、書いているブログと関係が深い物ばかりなのです。でも、一つ一つ、別々の物なのです。
個別の人名や企業名を書いたものはありましたが、住所やメールアドレスなどの記載はなく、すぐ、連絡をとって聞いてみるということは、実現しませんでした。でも、これを糸口として、何らかの連絡をとることは出来ると思いました。
でも、私は、次のブログを書く計画をたてており、共同執筆を依頼する人達も動いてくれています。当面は、そちらをしっかり実施しなければならないのです。
今日、このブロクを読んでくださった皆様、何かお手伝いいただけないでしょうか。
(注1) 地方販ハローワークとは、地方公共団体が運営する無料職業紹介事業所で、地域の雇用問題に対応するために設立された。これにより、求職者と求人者のニーズに応じたサービスを提供し、地域の雇用創出や生活支援サービスを一体的に実施することが可能になる。地方版ハローワークは、国のハローワークとの連携を強化し、地域の自主性を高めるために設置された。
(注2) 国のハローワークとは:厚生労働省が運営する公共職業安定所のことである。ハローワークは、求職者に対して職業紹介や求人情報の提供、雇用保険の手続きなどのサービスを無料で提供している。全国に500カ所以上あり、地域の雇用情勢に応じたサービスを提供し、求職者がスムーズに仕事を見つけられるようにサポートする。
(注3)介護のお助け隊は、介護に興味がある人や、仕事を退職した人、元気な高齢者などが登録し、介護事業所で介護の周辺業務に従事するプログラムである。具体的には、食事介助や入浴介助などの専門的な業務から、部屋の掃除や利用者の話し相手、レクリエーションの手伝いなど、専門的な知識を必要としない業務まで幅広く対応している。無資格や未経験者でも登録可能で、短時間勤務も受け入れている。
(注4) 日本経済新聞2025年8月23日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。①地方版ハローワークの開設自治体比率。(注)地方版ハローワークを開設している自治体の割合(2025年5月時点)。更生労働省の資料から作成。
(注5) 日本経済新聞2025年8月23日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。②地方版ハローワークの開設は北海道が最多。
(注6)日本経済新聞2025年8月23日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。➂地方版ハローワークの就職率は30%と国が上回る。
(注7)参照ブログ(1)2025年6月30日、転職人材、地方で厚遇、求人時の賃金、高知16%増、企業改革へ管理職Uターン。
(注8)参照ブログ(2)2025年7月11日、ゼブラ企業、社会貢献競う、鹿児島が最多、農産物EC代行、成長と両立、全国1.7万。
(注9) 参照ブログ(3)2025年7月28日、地場産業支える若き匠、岩手ファンクラブで大工育成、技能五輪入賞、地方が6割。
(注10)参照ブログ(4)2025年8月25日、移住誘うマルチワーク、島根県、夏は稲作、冬は酒蔵、人口急減、123組合が雇用し派遣。
(注11)参照ブログ(5)2025年9月22日、日韓自治体が協力で突破、島根県、IT導入や人口減対策。
(注12)参照ブログ(6)2025年10月13日、地方販ハローワーク浸透、希望聞き取り、雇用側とも交渉、全国990ヶ所、島根県は全市町村。
(1)日本経済新聞、2025年8月23日、朝刊(2面)。
[付記]2025年10月13日。
塾生から椎野先生への返信 金融研究会(角花菊次郎)
題名:労働力不足、熟考
労働力不足。企業は働き手を確保するのに四苦八苦という状態がもう何年も続いています。日本の労働力不足は1970年代前半の高度経済成長期が終わろうとする時期や1980年代後半~1990年代前半のバブル景気の時期にもありましたが、長期的な労働力不足は2010年代半ばに始まったと言われており、その主な原因は少子化と高齢化による生産年齢人口の減少と説明されています。
国内の生産活動の中心を担う15~64歳までの生産年齢人口は、確かに1995年以降減少が続き、2024年にはピーク時より15%以上減っています。一方で、働く能力と意思のある人を集計した労働力人口(15歳以上の就業者+仕事を探している人)は、女性や高齢者の労働参加が進んだことで横ばい推移というより、むしろ増加傾向にあります。実際に生産年齢人口に対する労働力人口の割合は8割程度(81.5%:2024年)とまだ2割ほど余力があります。もちろん、この数字は全国平均ですので、男女、年齢、地域によって余力にも当然、差が出ますが、一定の余力があることは事実です。したがって、ここで考えるべきは余力がある中で「労働力不足はなぜ起こるのか」という問題だと思います。
まず、労働力の「量的な不足」という問題に関して。前述のように労働力人口にはまだ多少の余力があります。問題は「業種間の偏在」による労働力不足です。具体的な業種としてはIT、建設、運輸、宿泊や医療・介護といった特定の分野で労働力不足が深刻化しています。IT技術の進化や少子高齢化、働き方改革による労働時間規制、慢性的な長時間労働といった労働条件の厳しさなどが背景にあり、全体的な労働人口の減少と特定分野の需要増加が相まって労働力不足を招いているのです。このような「人数」の偏在的不足に加え、実は労働「時間」の短縮化も進んでいます。短時間労働のパートタイマーが増加したことなどにより、労働者一人当たりの労働時間数(マンアワー)は1990年頃から一貫して減少を続けています。経済成長の源泉である労働供給が「人数」と「時間」の両面で制約を受けているのが、日本の現状と言えます。
一方、労働力の「質的な不足」という問題も指摘されています。つまり、企業が求めるスキルを持つ人材、あるいは企業にとって都合の良い安価な労働力が確保できないことが「人手不足感」の一因になっているという分析です。労働者が持つスキルと企業の求めるスキルが合致しなければ働く意欲があっても働けません。家事や育児、介護、余暇などと比較して労働対価が安ければ働こうとしません。企業は賃金を上げても求める人材が確保できなければ成長の機会を逃してしまいます。また生産性を上げて十分な賃金原資を確保できなければ企業は淘汰されてしまうことになるでしょう。「スキルと賃金のミスマッチ」、これが労働力不足のもう一つの要因です。
労働力不足の問題は、労働力の業種間での偏在と労働時間の短縮化という量的な面と、スキルと賃金のミスマッチという質的な面があることを確認してきました。しかし、労働力不足の問題はそれだけに留まりません。同じ労働力不足と言っても都市と地方でその背景が異なる部分があります。
都市と地方に共通する要因は、少子高齢化による全国的な生産年齢人口の減少、労働力の需給不均衡といった点になりますが、地方においては、若年層の都市部への流出、雇用機会の不足と職種が限られていることからくる偏り、賃金や労働条件の格差といった点、都市部では労働需要の増加、ハイレベルな人材の不足、人材の流動性が高いことなどが挙げられます。
以上のような、いわば構造的な課題にいかにして立ち向かうべきか。様々な処方箋が提言されています。自由に職を選べる環境を整えて「労働市場の流動化」を促進することが「適材適所」の実現につながる、大学院教育を拡充して人材のスキルアップを図るといった人材への投資、ロボットや生成AIを使った自動化・省力化によって生産性を飛躍的に向上させること、などなど。また、地方においては、自治体が独自に職業紹介を実施する「地方版ハローワーク」といった取り組みが為されています。
私たちの社会は労働力不足の問題に真剣かつ誠実に取り組んでいるとは思います。が、しかし、生産年齢人口が減少し、労働投入と国内需要が縮小する経済の停滞は確実に到来する近未来の姿です。そして社会保障費が増大する一方で税収は減少します。また地方では労働力不足や後継者不足が深刻化し、生活インフラや行政サービスが維持できずに廃止・縮小が進みます。さらにコミュニティの担い手が減少することで地域内の「共助」機能が低下し、防災や防犯に関するリスクが高まります。そのような暗く重たい社会が始まってしまったのです。
何が答えか、どうすればよいのか、私には分かりません。いや、誰しもその答えを探しあぐねている、ということだと思います。
しかしながら視点を少し変えてみると、労働力不足の主因である人口減少自体は悪いことばかりではないことに気が付きます。人口が減少することでエネルギー消費や廃棄物の排出量が減り、地球環境への負荷が軽減されます。都市部の過密や交通渋滞が緩和されます。そして、労働力不足へ対応する過程でAIやロボットなどの技術革新が促され、一人当たりの生産性が向上する可能性があります。東京一極集中の解消と地方分散型の社会モデルへ移行するチャンスになるかもしれません。
おそらく、私たちは「縮小均衡」社会への過渡期にいるのだと思います。その縮小均衡社会は、メリットとデメリットがバランスしたストレスの少ない社会になっているはずです。問題は過渡期に何年かかるのか分からないことです。一世代かかるかもしれません。薄々感じるのは、その過渡期に重い負担を担わされる不幸な世代が陽の目を見ずにただ我慢しただけに終わってしまうという悲しい未来の姿です。忍耐と覚悟。それが現代日本を生きる人々への究極のメッセージになってしまうのかもしれません。
以 上