□ 椎野潤ブログ(金融研究会第19回) 木材先物取引について(4)
文責:角花菊次郎
前回まではわが国において木材先物取引を導入する意義、その必要性について考えてきましたが、今回は導入にあたっての課題について少し考えてみたいと思います。
一言、「木材」を扱うといっても伐採木(timber)、丸太(log)、製材品(lumber)などそれぞれ生産・流通・加工の各レベルで取引が行われています。そして、丸太は原木市売市場において、柱や板などに加工された製材品は製品市売市場において取引され、それぞれセリによって価格が形成されています。原木市売市場ではほぼ100%、製品市売市場では9割方が国産材を扱っているようです。また、素材生産業者から丸太を仕入れて製材工場等に販売することや、製材工場等から製材品を仕入れて材木店・建材店当に販売するといった商いを行う木材問屋も木材流通を形成しています。この木材問屋はセリによって価格形成するわけではなく、相対取引が原則です。そこでは既存の取引関係、慣行など純粋な需給だけではない価格形成要因があるのかもしれません。なお、複数の木材問屋が集まって小売業者に販売する場所として、各地に木材センターが存在しています。木材センターは販売代金を回収し、手数料を徴収する業務を中心に行っていますが、扱う木材は輸入材がメインとなっているようです。
国産材の先物取引をスタートさせよう、と考えた場合、流通のどの段階を対象とするのかが課題の一つとなります。米国のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)では製材品(lumber)を取引しています。先物のような取引では、定められた規格、一定の品質、約定する数量の確保が守られていなければなりません。そのような要求を満たすためには、丸太の取引というわけにはいかず、必然的に製材品が取引の対象となるのでしょう。わが国においても、製材品の先物取引市場を念頭に検討を進めていくことになると思います。ただし、かつて合板の先物取引が実現一歩手前までいったように、流通全体の価格体系を決める起点はどこになるのか慎重に検討していかなければなりません。
また、国産材の先物取引価格は当然のことながら輸入材価格、シカゴ・マーカンタイル取引所先物価格の影響を受けることになります。そうであれば国産材の先物取引は木材価格の乱高下による影響を回避する機能などないのではないか、とも考えられます。しかし、CME価格の推移を見つつ、国産材と輸入材に纏わる需給状況、国際的な経済状況などを踏まえて双方のシェアを予想し、先物取引に投資するといった投機的機会を提供することでCMEにおける価格動向の影響を直接的に受けない、あるいは多少なりとも緩和する仕組みをつくる意義は大きいのではないかと考えます。このCME木材先物価格の影響についても検討すべき課題となります。
木材のような実物資産の先物取引では、「需給バランスの歪み」を先読みし、歪んだ価格が需給を適正に反映した価格に収れんする過程で投資利得を得ようとする行動がとられます。投資の世界で裁定取引(アービトラージ)と呼ばれているサヤ抜き取引があります。これは金利差や価格差に注目して、割安な投資対象を買い、割高な投資対象を売るポジションを取ることで、両者のサヤを抜こうとする手法です。この裁定取引が活発に行われることによって、原資産と先物取引価格との歪みが是正され、適正な先物価格が維持されることになるのですから、サヤ抜き行為で利得を貪るように見える行為も市場参加者が適正な価格で常に売買できる市場環境をつくるという意味で重要な役割を果たすことになります。そして、わが国で裁定取引が活発に行われるような国産材先物取引を実現するために問題となるのは、定格・定質・定量の実物資産たる木材を市場提供できるか、という点です。特に国産材では安定した供給量の維持が常に問題とされてきました。これらの課題に対応するためには、山土場を含めた集荷機能や輸送の最適化など流通全般に関わる効率化問題と需要に即応できる在庫機能の確立といった点について関係者全員で創意工夫し、解決に向けて注力していかなくてはなりません。
「国産材の先物取引市場」をつくり、価格変動リスクを低減しつつ国産材にかかる経営を安定化していくのだ、という強い意志。経済合理的な志。2025年は深刻度を増す経済情勢に背中を押されながらも一歩を踏み出すことができる年でありますように。
以 上
☆まとめ 「塾頭の一言」 本郷浩二
ロシアvsウクライナ戦争下・後の欧州情勢、びっくり箱のトランプ政策、世界中の大規模山火事の頻発や日本の輸入インフレで、社会・経済の情勢の不安定さが危惧され、次のウッドショックによる再度の乱高下の発生も懸念されている状況にある現在、国産材製品の価格の安定、そして安定的な価格上昇が絶対不可欠ではないかと考えています。
ウッドショックで木材価格が急騰して儲かって良かっただろうとの嫌味をお聞きすることがありますが、木材も含めた資材価格の急騰で建築物(特に住宅)の需要が冷え込み、その後の木材価格の下落も急で、価格も数量もずっと冷え込んでしまっている現在の状況を御存じないのでしょうか、と問い返したくなります。
また、価格転嫁が政府の重要な経済スローガンとなっていますが、需要と供給の相場で決まる価格では、この木材需給の冷え込みの中、雇用、物流、電気、燃料など必要なコストアップを価格転嫁もできません。製材所やプレカット工場などの淘汰が進んでいくでしょう。
皆さんが取り組まれている需要から遡って歩留まりの良い効率的な供給を実現するディマンドチェーンマネジメント、再造林可能な立木価格の実現を進めていくことは。個別事案の特殊解としては可能なものと思いますが、その特殊解を一般化、普遍化していくうえで、国産材製品価格の安定は一丁目一番地の課題だと思います。
定格・定質・定量の供給という先物市場を形成する条件は、国産材のサプライチェーンマネジメントを確立する条件と全く被っていると言ってよいでしょう。ですから、先物取引というものに対する関係者の心理的な障壁(相場リスクで危ないというような思い込み)をどうやって取り除いたら良いのかがまずは議論の入口としての問題なのかなと思います。合板の話もありましたが、今は、コメの先物取引市場構築のスッタモンダで、農林水産行政が先物取引に後向きであるという懸念もあり、どう進めたら良いのか悩むところです。皆さんも知恵を出してください。
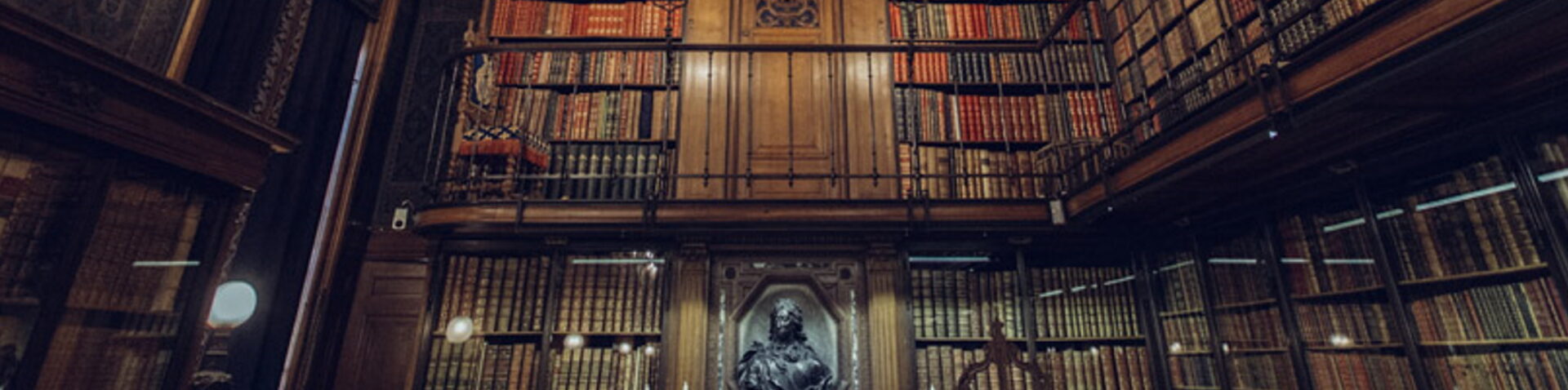

素人の質問ですみません。
”先物のような取引では、定められた規格、一定の品質、約定する数量の確保が守られていなければなりません。そのような要求を満たすためには、丸太の取引というわけにはいかず、、、、”
との事ですが、どうして定格・定質・定量が必要になるのでしょうか?
森村様
返信が遅くなってすみません。
あくまでも私見ですが、そもそも先物取引は、ある一定の価値のある物、客観的に誰が見ても同質の物(金・石油・穀物など)が、
市場環境や天候の影響を受けて価格が乱高下することの影響を相殺し、リスクマネーを投じる人にも利益があるようにする仕組みです。
原木の状態では品質が厳密にはわからないので、売る方は高めに言い、買う方は低めに見るため、上記の仕組みが機能しないのだと思われます。
もう一つ、ド素人の質問ですみませんが、
日本全国の森林伐採状況を、衛星データを使って4回/年、各都道府県毎にみていると、伐採が多く/少なく起こっている場所が、地域や時期ごとに見えてきました。このような”広域の伐採ムラ”情報が準リアルタイムで入手できるようになった場合、木材(原木?)先物取引市場が形成される可能性など、ありますでしょうか?
(”伐採ムラが、地域毎の原木価格の差につながっている”と仮定しています。)
前の質問で、一点、訂正させてください。”先物取引市場が形成される”事には必ずしもこだわらず、”価格安定の仕組みが作れる”可能性についての質問とさせてください。
森村様、またしても返信まで間が空いてしまい、大変失礼しました。
年4回、衛星画像で日本全国の伐採状況を確認されているというのはすごいですね。お仕事かご趣味かわかりませんが、とても興味深いです。
ただ、地域ごとに伐採量の差が大きいことと、原木価格の地域差がどの程度関連しているかは疑問です。
ご存知かと思いますが、木材産出量は、北海道・宮崎・岩手・秋田・大分・青森・熊本・福島の8道県で全国の54%を占めています。人口密度が低く、商工業が盛んでない地域が多いですよね。東京や千葉は森林面積はそれなりにあっても、林業の優先度は低くほんのわずかしか生産されていません。今後もその状況はあまり変わらないと思います。
木材の価格を安定させる仕組みは、松本氏が提案したような金融の手法を使う以外にも、製材・合板工場との長期契約など様々な手法があり得ると思います。中でも、私自身が過去にこのブログで何度か書いたように、山側が木造大型パネル工場を自ら運営し、サッシや断熱材の加工費の利益を含めた価格で工務店に供給する事業は、相場に左右されず山に利益を還元し、住宅資金が地域内で循環する経済を実現できる方法だと考えています。夢物語ではなく、最近幾つかの地域が手を上げて取り組みを始めています。よろしければ日経BPの「森林列島再生論」をお読みになってください。
丁寧に説明して頂き、誠にありがとうございました。もうすこし自分で勉強してみます。