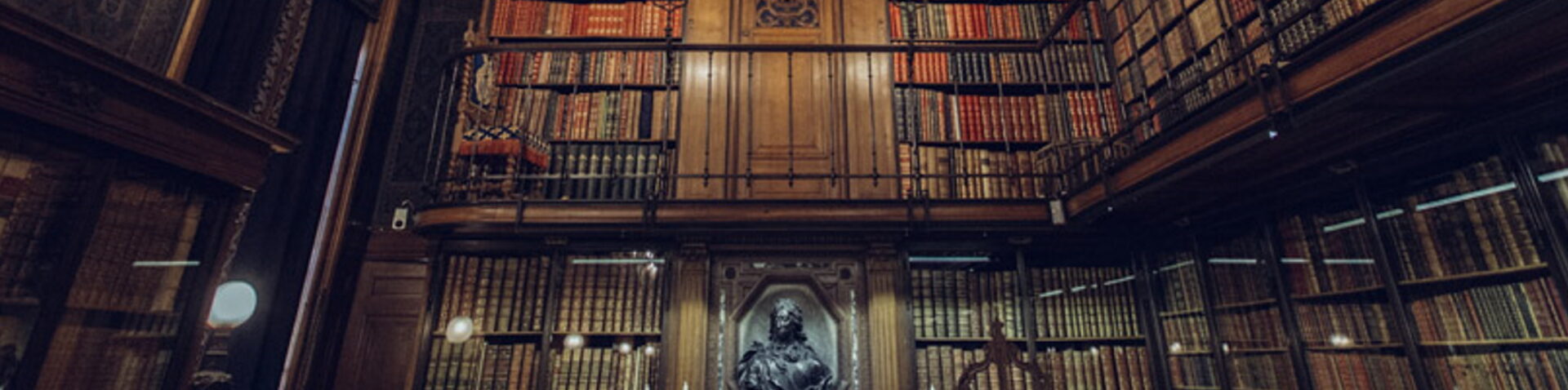椎野 潤(しいの じゅん) 2025年8(研究報告№148)
「巻頭の一言」
日本が目指す2050年までの、二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの排出実質ゼロに向け、自治体主導の「地域脱炭素」の動きが広がっています。省エネ、再生可能エネルギーの拡大で、全国のCO2排出量は2022年度までの9年間で23%減りました。京都市は、大手企業などへの削減計画義務づけが効果を上げ、寺社の再生エネの導入支援に取り組んでいます。2025年7月12日、日経朝刊、2面記事、(足立祐太、北村順司)を参照・引用して記述。
[日本再生][地域創生] 脱炭素、自治体が主導 京都市 寺社に再生エネや発光ダイオード(LED)17府県、排出25%以上減
ここでは日本経済新聞2025年7月12日、朝刊2面記事(足立祐太、北村順司)を参照・引用します。
「はじめに」
政府は2030年度に温暖化ガスを2013年度比で46%減らす目標を掲げています。環境省の都道府県別のCO2排出量推計で、最新の2022年度と2013年度を比べました。都道府県別の削減率をみますと香川県が41%と最も高かったのです。京都府など17府県が25%以上、西日本が多いのは原子力発電所が稼働した影響があるのです。
[京都市]
市町村向けの参考値である推計値によりますと、20政令市では、削減率は京都市が3番目に高いのです。これは、2004年制定の条例に基づく施策が後押ししているのです。その柱の一つが大規模排出事業者の削減計画の義務付けで、現在は140社が計画をつくっています。罰則はないのですが、市のホームページで進捗状況が分かる仕組みです。
酒造大手の月桂冠(京都市)は、2020~2022年度に温暖化ガスを大きく削減し、市から表彰されました。ボイラーなどの設備を更新し、エネルギー消費を可視化しました。また、そのためのシステムを順次稼働させました。製造本部長の泰洋二氏は「これまで生産現場では、水道のように蛇口をひねれば、いつでも蒸気が出ると考えていた」と振り返ります。
市は2022年度から一定の事業所面積をもつ中小企業に、エネルギー使用量の報告を義務付けました。市はCO2排出量を算出し、他企業と比べて多いか少ないか、フィードバックを返すのです。希望者には無料で専門家を派遣して省エネ診断をします。
2023年度は、寺社の太陽光パネルや発光ダイオード(LED、注1)照明の設置費用の補助を始めました。ただし、これは、電力は再生エネルギー由来のものに切り換えることが条件です。
北野天満宮は2027年の式年大祭「半万灯祭」に向けて、境内に3000個のLEDちょうちんを設置中です。禰宜(ねぎ)の東川楠彦氏は「神社は持続可能性の精神を受け継いできました。地域の模範として脱炭素をけん引したい」と話しています。
長年、環境政策に携わってきた岡田憲和副市長は「先進国に排出削減目標を義務付けた京都議定書の締結の地としての自負」があると力が入ります。
[山口県]
山口県では、出光興産や東ソー、トクヤマ、日本ゼオンなどの石油化学メーカーを中心に構成している周南コンビナート(周南市)が県と市と一丸となって、脱炭素化に向けて動き出しました。この4社が火力発電に使っていた石炭の一部をアンモニアに代替する体制づくりに乗り出し、県や周南市も支援体制を整えました。
4社が共有できる発電設備の新設構想も動き出しました。トクヤマの横田浩社長は6月に開いた記者会見で「コンビナート全体で最適の持ち方を考えた方が良いのではないかという議論をしている」と話しています。
県内は周南の他、岩国、宇部・山陽小野田の3地域でコンビナートを擁します。製造品出荷額に占める化学と石油の比率が2022年は5割を超え、脱炭素に対応しないと、県全体の産業に影響を与えかねないと、県は研究開発費、設備増強などを補助する基金を設立しました。
[おわりに]
温暖化ガス排出ゼロに向け、地域特性に応じた施策が重要になります。環境省は、2022年度から、自治体の提案に基づき先行的な施策を支援する、「脱炭素先行地域」を選定しています。
京都市の寺社の脱炭素などを全国88提案が選定を受け、実施に移っています。そのノウハウを各地で生かすことが重要です。日本経済新聞2025年7月12日、朝刊2面記事(足立祐太、北村順司)を参照・引用して記述した。
[まとめ]
この研究報告の執筆で参照・引用した、日本経済新聞の2025年7月12日朝刊2面記事に、三つの図表が記載されていた。①「CO2排出量削減率ランキング」。(注)環境省推計。CO2排出量を最新の2022年度と2013年度で比較した。削減率の高い順。
②政令市のCO2削減率。(観光省の自治体向け参考値)。➂全国ベースでCO2排出量は減っている。
[図表1]
図表1(注2)は、2025年7月12日の日経新聞紙上に、日本列島の地図として記載されていました。この図表は「CO2排出量削減率ランキング」と題した図表でした。そして、この「削減率のランキング」を5段階に分けて整理し、これを日本列島の地図の上に、緑色系の色彩で塗り分けて記述しました。これは以下です。
第1群は,「CO2の排出量削減率のランキング」において「削減率40%以上」(黒色)で示したところでした。
第2群は,「CO2の排出量削減率のランキング」において「削減率30~40%未満」(濃い黄緑色右斜線)で示したところでした。
第3群は、「CO2の排出量削減率のランキング」において「削減率20~30%未満」(濃い緑色)で示したところでした。
第4群は,「CO2の排出量削減率のランキング」において「削減率20%未満」(淡い黄緑色)で示したところでした。
次に、この第1群から第4群の各地域について述べます。
[第1群]
ここでは「CO2の排出量削減率のランキング」において「削減率40%以上」(黒色)で示したところを第1群と呼びました。
第1群に入っていたのは、全国第1位の香川県だけです。すなわち、第1群にはいっていたのは、この1か所だけでした。したがって、全国第2位からは第2群です。この香川県が、これまでの諸プロジェクトで、日本全体を牽引したことは、ほとんどなく新顔です。
[第2群]
第2群は、「CO2の排出量削減率のランキング」において「削減率30~40%未満」
濃い緑色右斜線に入っていた地域です。ここに入っていた地域は、愛媛県、佐賀県、滋賀県、和歌山県、徳島県、高知県の6ヶ所でした。ここに並んでいたのは、いつも上位にいる面々です。
[第3群]
この第3群は、「減少率が20~30%」濃い緑色の地域で、このプロジェクトでの主力メンバーの集団です。メンバーは以下です。北海道、青森県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、岐阜県、福井県、千葉県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県、愛知県、京都府、兵庫県、鳥取県、広島県、奈良県、大阪府、福岡県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県。ここには、まさに、堂々たる連中が並んでいます。今後、この中から、大躍進するところが出てきて、日本を代表する大リーダーになってくると想像しています。
[第4群]
第4群は、「減少率が20%未満」淡い黄緑色の地域で、最も削減量が小さい地域です。これは以下です。岩手県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、神奈川県、三重県、岡山県、島根県、山口県、沖縄県。この人達は、今回、立ち遅れています。この人達には、今後、大いに頑張ってもらわねばなりません。
[図表2]
図表2(注3)は、「政令市のCO2削減率(環境省の自治体向け参考値)」と題した図表でした。これは日本経済新聞の2025年7月12日の朝刊に掲載されていた図表です。これは以下の表です。
図表2「政令市のCO2削減率(環境省の自治体向け参考値)」
順位 「市」の名称 CO2の削減率
1位 熊本市 30.2%
2 新潟市 28.7
3 京都市 27.4
4 大阪市 26.9
5 仙台市 26.0
6 堺市 25.2
7 名古屋市 24.3
8 浜松市 23.9
9 広島市 23.8
10 川崎市 23.7
国は、現在、2050年までの二酸化炭素(CO2 )など温暖化ガスの排出実質ゼロに向けて努力を重ねています。これにより自治体主導の「地域脱炭素」の動きが広がっています。各市区町村では、CO2削減が進んでいます。
図表2には、政令市のCO2削減率のベスト10が記してあり、減少率の大きい順に示してありました。ここには、その順位、市の名称、CO2の削減(%)が記してありました。ここには、日本の代表的な都市が並んでいました。大阪市、京都市は上位に並んでいましたが、東京都の名がありません。日本の最大都市、東京都が、ここに出て来ないのでは困ります。東京都の奮起を期待します。ここでは、一位の熊本市の頑張りが目立ちました。以下、新潟市、京都市、大阪市と強者がならんでいます。
[図表3]
図表3(注4)は、「全国ベースでCO2排出量は減っている」と題した図表でした。これは日本経済新聞の2025年7月12日の朝刊に掲載された図表です。これは以下です。
図表の左側縦欄には、0、2、4、6、8、10、12億トンのCO2排出量(億トン)が列記されていました。また、横欄の下欄には、2013年度、16、18、20、2022年度と「年度」が記してありました。そして、この「CO2排出量」と「年度」を用いて「各年度別のCO2排出量」の棒グラフが書かれていました。
この図表では、2013年度の12億トンからスタートして、2022年度の9.5億トンに向けて、右肩下がりのCO2の排出量を示しています。2013年度の12億トンから2019年度の10億トンまでは、なだらかな下り坂で、2020年度かち2022年までの3年間は、9.5億トンで横這いでした。2022年以降は、さらに横這いが続くのか、さらなる、減少になるのかは、この図表からはわかりませんが、日本の未来を考えると、今後も一層の減少がつづくことを強く期待します。
(注1) 発行ダイオード(LED)とは、ダイオードの一種で、順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子である。
(注2)日本経済新聞2025年7月12日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。①CO2排出量削減率ランキング。(注1)環境省推計。CO2排出量を最新の2022年度と2013年度で比較。
(注3)日本経済新聞2025年7月12日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。②政令市のCO2削減率。環境省の自治体向け参考値。
(注4)日本経済新聞2025年7月12日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。➂全国ベースでCO2排出量は減っている。
(1) 日本経済新聞、2025年7月12日、朝刊(2面)。
[付記]2025年8月11日。
―金融研究会(角花菊次郎)椎野先生への返信―
題名:「脱炭素」という難問
最近、「SDGs」バッジを付けた人を見かけなくなりました。またもや、あれは流行りごとであったかと思えてきます。環境分野での環境ホルモン(外因性内分泌かく乱化学物質)、ダイオキシン、オゾン層破壊。地方創生分野では、まち・ひと・しごと創生総合戦略や一億総活躍社会。世界規模でのESG(環境、社会、ガバナンスを考慮した企業経営)やSDGs(より良い世界を目指すために行うべき国際的な行動指針)。どれもこれも、今はどうなっている?という話ばかり。解決できたから話題に上らないのでしょうか。
ちなみに、現在ビジネスが直面するDX(デジタル・トランスフォーメーション)、GX(グリーン・トランスフォーメーション)、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)はすべて古代ローマ時代のラテン語「trans-(向こう側へ、横断して)」を意味する「X」から派生しています。DXは2004年、スウェーデン発祥の言葉で、デジタル技術を基盤として、ビジネスモデルや組織、企業文化、顧客体験までを根本的に変革し、新たな価値を創出すること。GXは経済成長と環境保全を目指す活動、SXは企業が持続可能な社会の実現に向けて経営や事業を大きく変革することを表す言葉でともに2021年、日本発祥とのこと。もちろん、新たな言葉なり概念が生まれる時にはそれなりの背景があるはずなので、世の中が乗り越えるべきハードルだらけになっていることの裏返しですが、次々に新しい言葉が出てくると、本気で問題を解決したいと思ってその新しい言葉を作り出しているのか、疑わしく思ってしまいます。
さて、喫緊の世界問題、地球温暖化ですが、その原因とされているのが人為的な炭素量の増加です。IPCCという組織(気候変動に関する政府間パネル、1988年設立)が地球の平均気温が上昇しており、その主な原因が人為的な温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の排出であると断定しています。そのIPCC報告などを根拠として、1990年代に入り、気候変動枠組み条約締結国会議(COP)が開催されるようになりました。COPは1995年にベルリンで第一回会議が開催された後、1997年のCOP3で京都議定書が制定され、初めて温室効果ガスの削減行動が義務化されました。そして2015年のCOP21ではパリ協定が採択され、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて+2°より低く保ち、+1.5°以内に抑える努力をする、との国際的なルールを明文化しました。
このように温室効果ガス削減への機運が高まっていく中で、わが国でも2020年に当時の菅首相により、2050年に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことが世界に向けて宣言されました。とても大胆な宣言に産業界は疑心暗鬼に陥ったことでしょう。それまでわが国の企業は気候変動対策をあくまでCSR(企業の社会的責任)の一環として行ってきたのですから。
しかし、気候変動対策の視点を織り込んだ「脱炭素経営」を推進する企業が世界的に増加していく中で、企業活動における脱炭素活動の指標となる国際的な基準となるGHG(温室効果ガス)プロトコルが定められ、またRE100(Renewable Electricity100%)という再生可能エネルギーによる電力を100%使用する再エネ促進の国際イニシアティブがつくられるなど、わが国の企業も本気で脱炭素経営に取り組まざるを得ない状況となってきました。企業だけでなく、その企業に投資する機関投資家に対しては国連環境計画によってPRI(Principle for Responsible Investment):責任投資原則という環境負荷事業への投資抑制という投資原則が定められています。金融機関もFSB(金融安定理事会)によってTCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures):気候関連財務情報開示タスクフォースによる気候関連の情報開示等に関する提言に沿った対応を求められるようになりました。
世界の地球温暖化対策の潮流に乗って、わが国の産業・金融界は脱炭素へ向けた活動を活発化しています。ただ、脱炭素化には多額の投資が必要で、経済成長を阻害する側面があります。技術的にも完全に脱炭素化することは難しいといった課題があります。再生可能エネルギーはまだまだ非力で、炭素の塊である化石燃料に取って代われるほどのエネルギー源にはなり得ません。しかも、太陽光も風力も発電するまでの段階で相当の化石燃料を使うことになると言われています。原子力発電も問題山積です。本当に化石燃料を使わずに私たちの経済活動は成立するのでしょうか。
ただし、目下、企業は再エネ関連投資で稼ぎ、二酸化炭素の回収・貯留(CCS: Carbon dioxide Capture and Storage)やカーボンクレジット取引といった新分野のビジネスで稼ごうと目の色を変えていることと想像します。補助金頼みであろうと何であろうと、稼げるのであればそれはそれでいいとも思います。
「脱炭素」に象徴される私たちの経済活動が抱える難問、いや矛盾。
エネルギーが不足する、と深刻顔をされても、例えば、水道の蛇口を開けっ放しにしておいて、タンクの水が足りないと大騒ぎするのは愚の骨頂。炭素に依存した人間の経済活動そのものを抑制すること、が私たちに突きつけられている命題なのではないでしょうか。
問題は、炭素に頼って消費しすぎ、物を移動させすぎ、そして言ってしまえば人が多すぎるのです。人類が追い求めてきた「快適さ」と「便利さ」。そこが否定されているのだと正面切って発言する勇気。そこのところを問題解決の出発点としなければ、脱炭素話も「SDGs」熱が冷めつつあるように、地球温暖化に対する解決策はあたかも「脱炭素」ただ一つだというような「model=型」にはめただけの「mode=流行」に終わってしまう可能性大です。
以 上