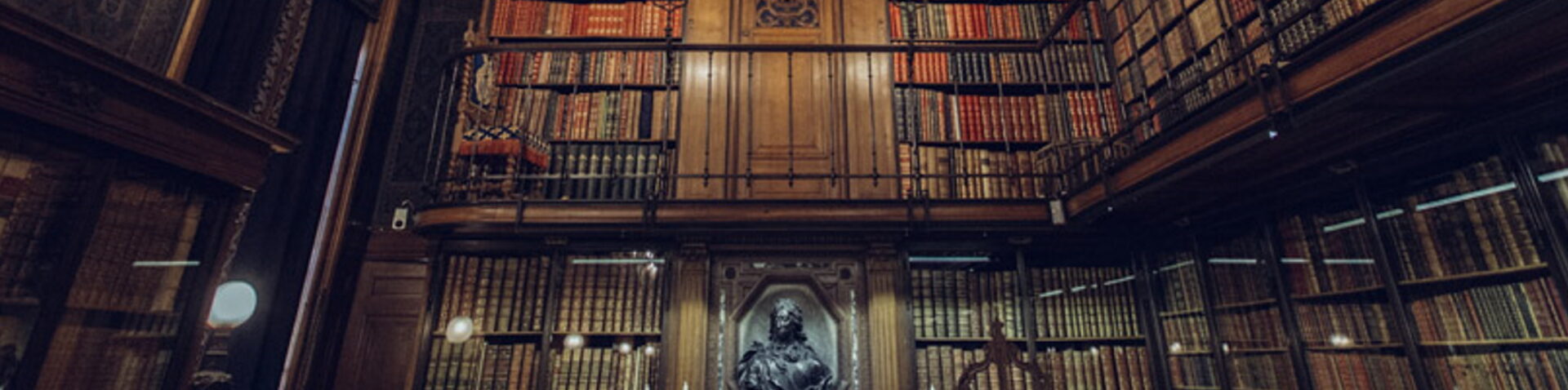椎野 潤(しいの じゅん) 2025年10(研究報告№154)
[巻頭の一言]
今日は、このテーマのブロクを書きます。でも、今回のブログは、いつもとは、チョットと違っているのです。まず、それを説明いたします。
実は、この論文で書く趣旨と、ほとんど同じ論文を、私が論文執筆を引退し、その後再開した時に、書いているのです。研究報告№002です。
それから3年後の2025年10月の、今、このテーマは大いに盛り上がったのです。そこで、ここでは、2022年10月7日のブログ(研究報告№002)を再発信し、これに続くものとして、新ブログを書くことにします。これによって、この間の3年間にこのテーマの改革が、どのように進展したのかが、良くわかると思うのです。
[引用するブログ]
世界の「大都市東京」の、この地における「新地域創生」(その2) 2022年10月7日、人口が多い東京都を地産地象の視点から 海水魚陸上養殖の近未来新産業の牽引に期待(修正版)
続木 碧(つづき あお) ※椎野先生のペンネームです。 2022年10月(研究報告№002)
このブログの標題について
近年、日本近海の漁獲量が減少しています。この対策として全国で、養殖漁業が拡大しています。近未来の2030年には、養殖漁業の漁獲が漁船漁業を上回るだろうと、新聞は予測しています。海のない内陸県で海水魚の養殖が続々と成功しており、次世代に向けて有望な産業になると期待されています。このような状況の中で、大きな課題を抱え、地産池消で有利な立場にある「大都市東京」が、「陸上海水魚養殖」の新産業での注目の牽引者になると、2022年のブログで、私は予想しています。
一方、東京で海水魚陸上養殖が始まったという情報には、まだ接していませんが、中長的に見れば、最大人口を持つ東京の鮮魚需要は最大で、地産地消の視点からみて極めて有利な東京都の海水魚の陸上養殖事業は、次世代の重要戦略になると、私は、かねてから
感じていました。すなわち、ここでは最高の鮮度の養殖海水魚が、最小の運賃で届けられるはずなのです。
引用文献[日本の誇る世界の大都市東京。この地における「新たな地産消」。]
この報告の主要な内容は、世界に誇る大都市東京の陸上養殖海水魚養殖事業についての記述です。以下に記します。
[調査研究報告 陸上養殖海水魚養殖事業]
ここでは日本経済新聞の2022年10月7日(岩崎貴行執筆)および同日(久保田告喜、兼谷将平、上野正芳、桜井裕介執筆)の記事を紹介します。
[埼玉県]
県の最北端に位置する神川町。県内を中心に温浴施設の運営を手掛ける温泉道場の「おふろcafe白寿の湯」に2021年10月、サバの陸上養殖場が設置されました。海のない埼玉県で、おいしく新鮮なサバが食べられるようになると話題になり、地域活性化に向けた期待が高まっています。
養殖場には3基の水槽や濾過装置が備えられています。開設当初に投入したサバの稚魚は順調に育っています。今年4月に、稚魚を追加投入し2023年5月には、出荷の第1号が市場に出る見込みです。
海のサバにはアニサキスがいることがあるため、生食は勧められないのですが、管理された設備で育つ養殖サバは、生で食べられるのが強みです。温泉道場の担当者は、「日々水質管理に努め、質の高い養殖サバを提供したい」と意気込んでいます。
[群馬県]
埼玉県と同様に海がない群馬県でも、太陽光発電の建設を手掛けるジースリー(同県伊勢崎市)が、ウナギを養殖しています。前橋市内の1万6000平方メートルの敷地に、複数の水槽が入ったハウス3棟と太陽光発電所、蓄電システムを備えています。汲み上げた地下水を太陽光発電で温めることで、養殖池をウナギの生育に最適な温度に保ちます。
2019年から飼育を開始しました。現在は30万匹のウナギを養殖しています。伊勢崎市内にウナギの加工場も新設し、2022年8月に稼働させる予定です。金子史朗社長は、「ウナギを収益源にしたい」と意気込み、地域の名産品を目指しています。2022年6月18日の日本経済新聞(岩崎貴行)が、この記事を書いていました。
[滋賀県]
滋賀県甲賀市でも、民間業者がトラフグやヒラメなどの養殖を始めています。寄生虫やウイルスの影響を避ける狙いで、人工海水を使用しています。さらに、養殖魚の糞尿などを分解するバクテリアで、養殖水を浄化し養殖水を繰り返し使用することで,周辺環境に悪影響を及ぼす排水を出さないのです。すなわち、ここでは関係者が、一致団結して養殖漁業を推進しています。2022年6月18日の日本経済新聞(久保田酷基、兼谷将平、上野正芳、桜井裕介)が、この記事を書いています。
[まとめ]
漁業界では、最近は毎年、沿岸漁業の不振が続いており、その延長線上で、近未来の魚類資源の枯渇が危惧されています。それに対する対策として、漁船漁業から養殖漁業への転換が、積極的に進められています。各地で様々な工夫がなされており、「徹底的に売れる商品(養殖魚)作り」を目指して各地が切磋琢磨しています。
この研究報告は、「大都市東京(注1)」が、「新たな地域再生」を目指す視点を直視して記載していますが、私は、今の現実では、まだ、創出されていない、大都市東京(注1、東京、神奈川、埼玉、千葉)」における中心都市「東京都内」の「陸上海水魚養殖事業(注2)」が、ポストコロナ後の「新地域再生」の重要事業になると睨んでいたのです。鮮魚は鮮度が命です。ですから、徹底的に地産地消にするべきです。私は、最大需要の存在地「東京都」も、「陸上海水養殖事業」のメッカ(注3)になるはずだと確信しているのです。
東京都が、この事業領域のリーダーになって、はじめて、この研究報告のシリーズのメインテーマである「山間地域とは別の地域創生」すなわち「大都市で地域を創出する地域創生」の開幕となるのです。
参考資料
(1)日本経済新聞、2022年6月18日(岩崎貴行執筆)。
(2)日本経済新聞、2022年6月18日(久保田酷喜、兼谷将平、桜井裕介執筆)。
[付記]2022年10月7日。
ここまで、私が3年前に書いた、古いブログを読んできましたが、この陸上の養殖漁業は、この3年間の大いなる頑張りで、凄く立派に育っていたのです。それを、今、このブログで書いています。以下にこれを報告します。
[新たに執筆するグログ]
陸上養殖 海なし県で育つ 岐阜県 トラフグをブランド化 国内販売2030年 1700億円
椎野 潤(しいの じゅん)2025年10月(研究報告№154)
[巻頭の一言]
水産物を陸地の施設で育てる陸上養殖が全国で広がっています。水産庁への2025年1月1日時点の届け出では740か所でした。前年に比べ78ヶ所増えました。岐阜県の事業者は「飛驒とらふぐ」のブランド化に成功し、各地にノウハウを伝授しています。海なし県発の技術が日本の漁業を深化させています。日本経済新聞2025年9月13日、朝刊2面記事(鈴木泰介)を参照・引用します。
[はじめに]
水産庁によりますと、海水魚陸上養殖は、水槽や水質管理設備の初期投資、水温を保つ電気代がかさむのですが、温暖化による水温上昇や津波による被害など、天候や気象、海洋環境に影響されにくく安定供給しやすいのです。
ろ過した水を循環させる閉鎖循環式水槽(注3)などを対象に、陸上養殖は2023年4月に届け出で制となりました。ウナギの養殖は、農相の許可が必要な届け出対象外ですが、「届け出制だったら対象になるようなウナギの陸上養殖はまだ少ない水準」と水産庁栽培養殖課は言っています。
富士経済によりますと、循環式水槽で陸上養殖した水産物の国内販売額は、2024年実績では、239億円です。2025年は6割増の455億円となる見込みです。「大規模な陸上養殖施設の開設や計画が相次いでいる」として2030年には1700億円まで拡大すると予測しています。
[沖縄県・大分県・鹿児島県、岐阜県]
都道府県別では、海ぶどうの生産が盛んな沖縄県が、陸上海水魚養魚施設の建設が、196ヶ所で最も多く、「かぼすヒラメ」などの大分県が54か所、クルマエビの生産が多い鹿児島県が34か所で続きました。
第4位の岐阜県は32か所で、海無し県下では最多です。ブランド魚として定着した「飛驒とらふぐ 」は、岐阜県飛騨市の飛驒海洋科学研究所(注4)が試行錯誤の末、約5年かけて安定的に育つ塩分濃度や水温を突き止め、2010年ごろ出荷を始めていました。研究所の深田哲司社長は現在、ノウハウの伝授に軸足を置いています。その一つ、地域活性化に取り組む岐阜県高山市のTry-win(注5)は温泉水でウナギを養殖しているのです。下呂温泉の元湯から、ほどよく離れたところの平均28度ほどが、ウナギの養殖に適しているのです。冬に5~10度になる川の水を温める必要がなく、燃料費の節減にもつながります。
2025年7月から本格的に販売を始めサーモンやヒラメといった他魚種の生産も見据えています。岐阜県下呂市には温泉施設やプールなど遊休施設が多く、行政と活用策で連携しています。
[奈良県]
奈良県天川村は、村が主導して廃校でトラフグを養殖しています。冬場の新たな観光資を探していた村役場が企画し、岐阜県の深田社長の技術指導を受けたのです。2024年から地元の旅館に出荷しています。
[滋賀県]
異業種の参入も相次ぎます。滋賀県長浜市のプリント基盤メーカー、ワボウ電子は200年にハナベイエビの養殖を始めました。本業の技術を生かし立命館大学と水質管理センサーの部品の共同開発を開始しました。これは新規事業としてもシニア社員の活躍の場としても成果を生んでいます。一度に40万匹の飼育が可能で「おうみ海老」として関西圏や東海地方の飲食店などに卸しています。
[鳥取県、富山県、愛知県、長崎県、福島県]
大手企業の参入も、目立ちます。JR西日本は、沿線の活性化を目的に2017年から陸上養殖事業を始めました。鳥取県でサバ、富山県でサクラマス、愛知県および長崎県でヒラメなどを地元と協力して広げています。
NTT東日本は、ICT(情報通信技術)を使い、水温や塩水濃度を遠隔で常時把握し、福島市でベニザケをそだてています。NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーショズ)は子会社を通じ陸上養殖事業を外販しています。
[おわりに]
陸上養殖に詳しい東京海洋大学の遠藤雅人准教授は「陸上養殖は広がってきたが、輸入が多い稚魚の安定調達や販路拡大など採算性の確保のハードルが高く撤退例も多い。継続発展には、国産の稚魚を増やし、特産品を使った餌や加工品の開発などによる養殖魚のブランド化が欠かせない」と話しています。日本経済新聞2025年9月13日、朝刊2面記事(鈴木泰介)を参照・引用し記述しました。
[図表1]
2025年9月13日の日経新聞紙上に、2025年1月1日時点の「陸上養殖の届け出数ランキング」と題する図表が記してありました。これを図表1(注6)としました。
この地図に示された地域は、4群で構成されています。次にこの4群を整理しておきます。
(1) 第1群、届け出で数が20ヶ所以上のところ。
(2) 第2群、届け出で数が10~19ヶ所のところ。
(3) 第3群、届け出で数が5~9ヶ所のところ。
(4) 第4群、届け出で数が4ヶ所以下のところ。
次に、この第1~4群の内容について述べます。
[第1群]
ここで第1群は、陸上養殖の届け出数が20ヶ所以上の処です。この届け出数を都道府別にまとめますと、第1位は沖縄県、第2位は大分県、第3位は鹿児島県で、この後に、北海道、岐阜県、山口県、長崎県、熊本県、愛媛県がこれに続いていました。第一群はこの9か所でした。第1群は九州が5か所(沖縄県、大分県、鹿児島県、長崎県、熊本県)と著しく多く、本州は、岐阜県と山口県の僅か2か所のみでした。
[第2群]
第2群は、陸上養殖の届け出数が10~19ヶ所の処です。ここに入っていたのは以下です。新潟県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、宮崎県、高知県でした。第2群は、この13ヶ所でした。第2群はだいたい全国満遍なく広がっていました。三大都市では大阪府は第2群で頑張っていましたが、東京と京都は第3群でした。
[第3群]
第3群は、陸上養殖の届け出数が5~9ヶ所の処です。ここに入っていたのは以下です。岩手県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、和歌山県、鳥取県、和歌山県、香川県、徳島県でした。第3群は、この16か所でした。
[第4群]
第4群は陸上養殖の届け出数が4ヶ所以下のところです。ここは届出数が最小のところ ですが、ここには10所入っていました。ここに入っていたのは以下です。これは、青 森県、秋田県、宮城県、栃木県、富山県、石川県、福井県、三重県、島根県、佐賀県で す。第4群は10か所でした。
[図表2]
図表2(注7)は、「陸上養殖の届出数ランキング」と題した図表でした。これは日本経済新聞の2025年9月13日の朝刊に掲載されていた図表です。これは以下です。
この図表2では、陸上養殖の届出数のランキングについて、海ブドウから、サケ・マス類まで、その20ヶ所以上から4か所以下まで、届出数の多い順に記していました。これを表にして列記します。
図表2 陸上養殖の届出数ランキング
順位 陸上養殖の種類 届出数
1位 海ぶどう 165
2位 ヒラメ 126
3位 クルマエビ 107
4位 トラフグ 93
5位 バナベイ 87
6位 サケ・マス類 82
7位 その他 523
(注)2025年1月1日現在。一か所で複数届出し、育てている場合がある。
図表2(注7)は、陸上養殖の届出数について、その届出数の大きい順に記してあります。
この図表2を見てみますと、陸上養殖の届出について、その届出数が最も多かったのは「海ぶどう」であり、その数は165ありました。第2位は「ヒラメ」の126でした。以下、「クルマエビ」107、「トラフグ」93、「バナベイエビ」87、サケ・マス類の82でした。
[図表3]
図表3(注8)は、「陸上養殖水産物の販売額は拡大が続く」と題した図表でした。この図表3の左欄縦欄に、0、200、400、600、800、1000、1200、1400、1600(億円)と記してありました。また、下欄横欄に、2021年、23、25、27、2030年と「年」が記してありました。この「年」と「陸上養殖水産物の販売額」を用いて、「陸上養殖水産物の各年の販売額」の棒グラフが書いてありました。
この棒グラフを見た結果、以下のことがわかりました。
陸上養殖水産物の販売額は、この販売が始まった2021~2023年頃には、販売額は少なく、年100億円程度に止まっていました。2024年から増加が始まり、2025年までに1000億円位にまで拡大しました。ここから急成長が始まり、2027年には1600億円の売上が予測されています。2030年には、1600億円に達することが期待されています。
(注)これは循環式の陸上養殖を示したものです。出所は富士経済。
[まとめ]
「海水魚の陸上養殖」は、私が、2022年にブログに書いてから、「日本の今後の成長の停止」の不安を、払拭する手段として、考え続けていたテーマでした。
それが9月13日の日本経済新聞朝刊に、再び掲載され、その後の3年間、この活動が、全国各地で、熱心に実施され、随分本格的になっていることを知り、私は喜びました。でも、全国各地での実施地域は、前回のブログで書いていた処とは、今回は、全て違っていました。すなわち、2022年に、「海水魚の陸上養殖」が、開始されていた地域は、埼玉県、群馬県と滋賀県でしたが、2025年の今回は、沖縄県、大分県、鹿児島県、岐阜県と、奈良県、富山県、愛知県、長崎県、福島県で、この3年間に、実施地は全国に広がりました。そして、2022年に記述があった、埼玉県、群馬県、滋賀県については、全く記載がありませんでした。これらの各地は、今も熱心に活動しているだろうと、私は思っておりますが、情報が、丁度伝わるタイミングではなかったのだと思います。
2025年の記事で見ますと、九州の活動がきわめて活況をとげているのです。沖縄県、大分県、鹿児島県、長崎県と4県が活動県として挙がっており、その活況ぶりは、素晴らしいものがあるのです。また、全般に、日本列島の中央部とその西側に、強い活気がありました。岐阜県、富山県、愛知県、鳥取県など、きら星のように、活躍する地域が並んでいます。
また、これまで報告してきた多くのプロジェクトの中で、第1群は20都道府県と、とても数が多いのです。これだけの数の第1群の地域があれば、切磋琢磨して競いあって改革を進めれば、改革は一気に進むと思われます。私は、この先進集団を、なんとか後押しして進めて行きたいと思いましたが、今回、記載された記事には、具体的な活動の詳細な情報の記載は、多くはないのです。岐阜県の活動については、丁寧に書かれており、奈良県や滋賀県についても記載されてすいますが、第1群の沖縄、大分、鹿児島、北海道、山口、長崎、熊本、愛媛については、岐阜のような具体的な活動の報告は、まだ、良く見えないのです。
これらの地域を中心とした、第2弾目の情報が報告されて、日本各地の人々が、これを参照できる日が、一日でも早く来ることを、私は熱望しています。このブログをお読みの読者の皆さま、お手許に情報をお持ちの方は、是非、ご提供いただきたく、よろしく、お願いいたします。
(注1) 大都市東京:私が「日本の誇る大都市東京」と呼ぶ地域は、東京都だけでなく、これを囲む地域である神奈川県、埼玉、千葉県までを広く含めている。
(注2) メッカはイスラム教の第1の聖地である。転じて、ある分野の中心地や発祥地、あこがれの地をメッカと言う。
(注3) 閉鎖循環式水槽は、海水に生息する魚介類の養殖を行うための陸上養殖設備である。この設備では、使用される海水は脱窒まで行って完全に濾過され、再利用される。閉鎖した設備の中で環境を管理するため、赤潮、ウイルス、魚病、荒天等の外的要因を受けにくく、歩留が高いのである。また、年間を通じて水温を調整できるため、養殖期間が短くなり生産性が高まる。
(注4) 飛驒海洋科学研究所は、岐阜県飛騨市に位置する企業で、主にトラフグの養殖技術を開発している。この研究所は、陸上養殖の技術を確立し、地域の水産業を活性化するための取り組みを行っている。具体的には、温泉水を活用したウナギ養殖や、廃校を活用したトラフグ養殖など、地域ブランドの魚を育てるための技術を提供している。
(注5) 株式会社トライウイン(Trywin Co.,Ltd.)は、神奈川県横浜市港北区に本社を置く日本のデジタル機器開発メーカーである。ポータブルナビゲーション、ブランドの「if(イフ)」、 ワンセグチューナー、 携帯電話バッテリーなどの開発を手掛けている。
(注6) 日本経済新聞2025年9月13日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。①陸上養殖の届出数ランキング。
(注7) 日本経済新聞2025年9月13日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。②種類別の内訳。
(注8) 日本経済新聞2025年9月13日の日経朝刊2面には、三つの図表が掲載されていた。➂陸上養殖水産物の販売額は拡大が続く。
(1)日本経済新聞、2025年9月13日、朝刊(2面)。[付記]2025年10月20日。
塾生から椎野先生への返信 堀澤正彦
椎野先生のブログ再開、心から感激しています。現代林業で連載されたロジスティックゼミ第一回を読んでから、これまで悶々としていた林業への疑問が一機に解けるような気がして、先生のブログを読み漁りました。一時は、引退とのことで私たちが担ってきましたが、再開されたブログで新たな刺激を得られることは大いなる喜びです。
そして始まった往復書簡の弟子からの返信。錚々たる顔ぶれの後、不肖の私にも順番が回ってきました。
提起された話題は陸上海水魚養殖。海なし県の岐阜や埼玉が海水魚のブランド化を頑張っていることを読み、まずは地元長野県のブランド養殖魚「信州サーモン」はどうなっているのかと思いましたが、信州サーモンはニジマスとブラウントラウトを交配した淡水魚なので、ニュースソースとしては土台が違うことに気づきました。
長野県は旧来からイワナやニジマスなどサケ科の淡水魚の養殖が盛んでした。特に、ニジマスはかつて北米に多く輸出されていましたが、1970年代に為替が変動性になったことで価格競争力を失い、魚類養殖自体が長らく冬の時代を過ごしていたようです。そのような状況下で、あらたに開発されたのが信州サーモンです。皆さんは口にされたことはあるでしょうか?ほどよい脂ととろけるような舌触りで臭みもなく、海水養殖のサーモンにも勝ります。昨今の社会情勢から、ノルウェーサーモン代替として需要が増大しているとのことです。そう、信州サーモンも頑張っているのです!
さて、前置きの話題が長くなりましたが本題です。魚類養殖には、ブランド化による付加価値増大のほかに大きなメリットがあります。椎野先生の記述にもありますが、それは品質と生産(供給)の安定性です。特に、海から遠い内陸地域でも、複雑な流通経路を省き、安定した価格や供給を享受することができます。これは林業も参考にしなければなりません。
日本は、膨大な人工林資源があるにもかかわらず、長年にわたり輸入木材依存で低調な自給率に甘んじてきました。その原因は様々で一概には言えませんが、旧来には建築と森林が一体であった地域木材の流通が分断したことが一因であることは間違いありません。成熟した森林の利活用が進まずとの表現を多く見かけますが、裏を返せば豊富に在庫があるということです。都市平野部でも都道府県レベルで見渡せば意外と近くに人工林が存在するのです。
適材適所、樹種や材質を勘案すると、近くに人工林があっても手放しで利用できるわけではありません。しかし、最短距離で建築と森林をつなぐ、食の魚類の陸上養殖に負けないような流通の再構築をあらためて志向しなければならないと思いを新たにしました。
以 上