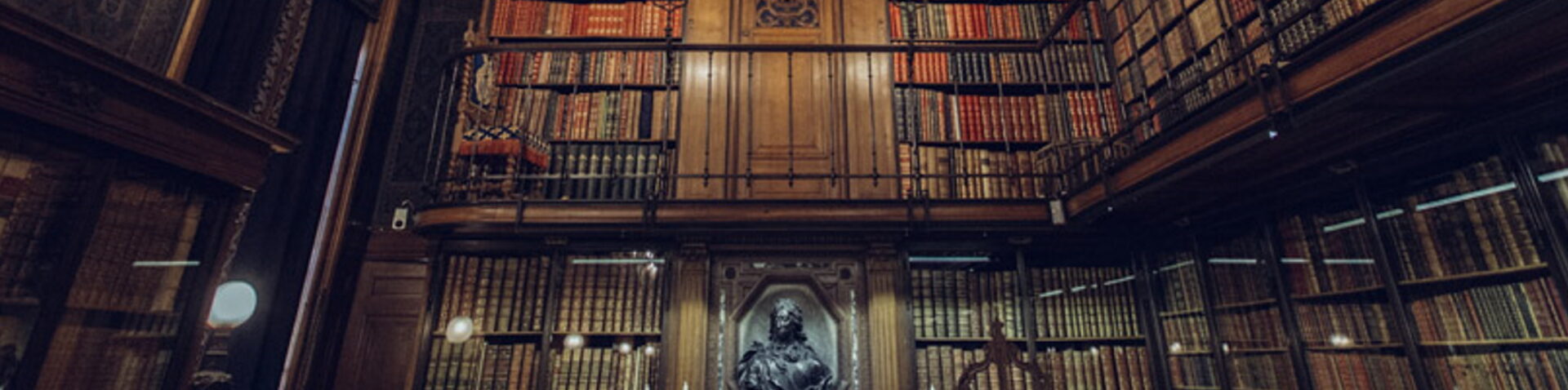□ 椎野潤ブログ(塩地研究会第50回) 佐伯広域森林組合と歩んだ道③
佐伯広域森林組合 柳井康彦
6.山と工場をつなぐ
平成27年には再び山の事業へ異動となり、山側と工場の連携を強化する業務を担わされました。話は戻りますが、佐伯広域森林組合は各部門でそこそこの利益をだしながら進んでいましたが、やはり工場のウエイトが大きく(年間10万m3以上の原木消費)この武器がいかされる一番良い形はどうなのかという内部意識が全体に生まれだしたのはこの頃からであったと思います。山からの原材料をある程度コントロールできる製材所はどこよりも強さがあるはず。組織体制と原木の流通体制を見直し、佐伯広域森林組合にとってベストな体制はどうなのかに取組みだした時期でした。ここに至るにはかなりの時間と経費がかかったと思います。※塩地氏の一言 「君たちはエセ製材所か」ちがうやろ。「山をどうするかの為の業務をやってるやろ」の鼓舞。(たまに心にぐっとくる事をいってくれるんです)改めてこの一言に感銘と自信をもてたのも事実です。
工場の生産計画に合わせた原木集荷。原木の在庫量と仕入れ量の調整。それに合わせた伐採計画、採材指示。出材される原木の工場不必要材の販売対策。※わがまま工場(山側目線)に合わせる原木供給側の職員は不満もでてきますが、このサイクルがベストであることを組織全体に認識(強制認識であったかも)させました。しかし現実は天候に左右された原木不足やら、逆に運搬が困難なほど山土場にたまってしまった原木現場が発生したり、机上のとおりにはいきません。頭の痛いネタはたくさんありました。
佐伯広域にはアドバイザーという雇用の方がおられます。県OB、民間OB、システム関係(PC)、県警OBなどが数名。私よりも年配であり経験豊富な方々です。管理職としても相談(愚痴)ができる環境があったのはありがたい事でした。
この地域では主伐後に再造林を行う事はあたりまえの事としてやってきました。工場と山側の連携もいまだに試行錯誤しながら日々の業務を行っています。伐採現場の残材をバイオマス材として搬出し再造林への資金に充当する。再造林後は5年間の下刈りを実施しその後も除伐・間伐し所有者へ安心感のある方向で事業をお返しする。数年間をかけてこの形にたどりついたと思います。まだまだチャンスと伸びしろはあります。
今回、1森林組合の職員目線を題材にとりあげてくださり感謝いたします。私は佐伯市宇目の田舎町で森林組合という職場を通じて日本全国に出張しました。商社、市場、ハウスメーカー、プレカット様等々。たくさんの人と出会い、貴重な経験ができた職場でした。
森林組合の職員とは一般の方ではわかりづらい山林の場所をいくつかの図面、情報で把握し、平地ではない土地の立木を評価する。評価とは立木そのものの収穫期を決定し、その量と売上価格から作業方法毎の経費を引いた金額です。また、その後の再造林についても方向性を示し所有者へ管理上の安心感含めお返しする事までができて初めて1人前です。その業務を行うにはそれなりの失敗経験も多々必要です。マニュアルでは通用しないのが山の現場なんです。失敗の数が経験値でもありそれを前向きに業務に活かす。こういった環境で業務をおこなえた事が精神的にもありがたい事でした。直近の佐伯広域森林組合はまだまだ成長しているように感じます。一方で停滞している自分がみえてきました。あと一か月で定年退職(寄稿は2025年2月)。最後にこういった機会を頂き本当に感謝いたします。
☆まとめ 「塾頭の一言」 本郷浩二
柳井様、定年ですか。誠に長い間、お疲れ様でした。まだまだ、お元気で、色々な形、局面で、佐伯広域森林組合や地域の林業・木材産業の発展にご支援くださればありがたいです。
所有者へ管理上の安心感を含めてお返しする、ということが強調されていて、この考え方が佐伯広域の経営理念ということと理解しました。その経営理念が確固たるものであったればこそ、佐伯広域も柳井様ご自身も、どんな難題や失敗、頭痛のネタにもしっかり対処してこられたものと思います。森林組合にとってお荷物になりがちな工場を武器にすることができたのも、その理念を突き詰められた結果に外ならないと思います。
森林組合は森林所有者の協同組織であることの基本の部分がしっかりと根付いていて、柳井様が退職された後も、他の役職員の方々に引き継がれていくことが確信されているようですから安心ですね。
世の経営に悩まれている森林組合には、ぜひ、佐伯広域が歩んでこられた道をこの経営理念の切り口から学ばれて、それぞれの地域の森林・林業の未来を形作ってもらいたいものです。