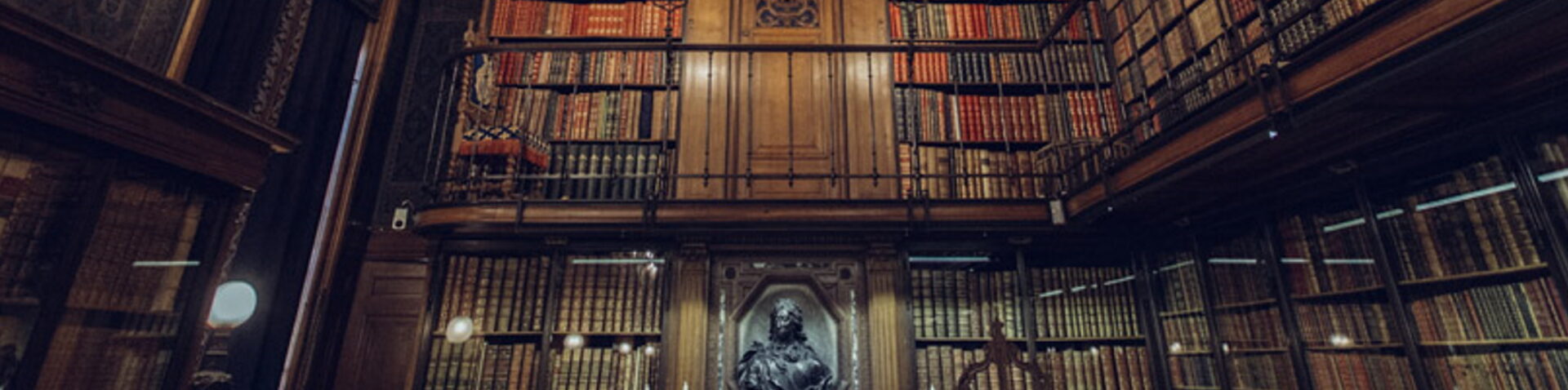□ 椎野潤ブログ(伊佐研究会第22回) 全国植樹祭と、秩父に息づく本多静六博士の精神
まもなく令和7年5月25日、第75回全国植樹祭が埼玉県秩父市で開催されます。この記念すべき節目の行事が、私たち森林パートナーズの拠点である秩父で行われることに、深い喜びと誇りを感じています。有難くも森林パートナーズのプラットフォーム参画企業6社とともに招待していただき参列致します。
秩父は、古くから豊かな森林に恵まれ、その資源とともに人々の暮らしや文化を育んできた地域です。一方で、林業の衰退や山村の過疎化といった時代の波に直面してきた場所でもあります。私たち森林パートナーズは、「木を使って山を守る」という理念のもと、山林所有者、製材所、プレカット工場、地域工務店、そして都市の生活者をつなぐ新たな木材流通の仕組みを構築し、山に利益を還元するモデルづくりに挑んできました。この地で全国植樹祭が開催されることの意義は大きく、あらためて「木を植える」ことの意味を深く考えさせられます。
全国植樹祭の原点には、日本初の林学博士であり「日本公園の父」と称される本多静六博士の思想があります。明治期にアメリカで「アーバー・デー(植樹の日)」を視察した本多博士は、日本でも国民的な植樹行事を行うべきだと提唱しました。特に天長節(天皇誕生日)に、陛下の御親植を中心とした式典を通じて、全国民が森林への思いを一つにする機会とする構想でした。
当時はこの構想は実現に至りませんでしたが、その精神は時を経て昭和25年に形となり、全国植樹祭として制度化されます。埼玉を愛し、かつて秩父大滝に広大な山林を所有し、晩年まで足を運んだ本多博士にとって、この地での開催はまさに象徴的な出来事です。博士も天上で喜ばれているに違いありません。
当社代表・伊佐裕は、新たな木材流通を通じた秩父産材の活用と森林再生の取り組みにより、第17回「本多静六賞」を受賞いたしました。本多博士の理念と共鳴する実践を評価いただいたことに、改めて感謝の思いを深くしています。
第1回全国植樹祭の少し前、昭和22年に昭和天皇が詠まれた御製があります。
こりて世にいだしはすとも美しくたもて森をば村のをさたち
木を伐って木材として世に出すことはあっても、美しい森を保ち続けるようにと、村々の指導者たちに呼びかけるお歌です。戦後の復興で木材需要が高まる中にあっても、伐れば植える、森を守るという心を失ってはならないという、植物学にも深い造詣をもたれた昭和天皇の祈りが込められているように感じます。本多博士が植樹祭を提唱したのも、近代化の波による森林の乱伐に強い危機感を抱いたことが背景にありました。
そして現代では、木を伐っても林業に利益が残らず、人手不足や苗木の確保難、さらには獣害対策の高騰などが再植林を困難にしています。こうした悪循環が全国で蔓延し、日本が世界に誇る森林資源の再生を妨げています。国民が森の現状を深く理解し、行動につなげていくためにも、全国植樹祭の持つ意義は改めて大きなものであると実感します。
今年、陛下の御臨席のもとで行われる全国植樹祭。その背後には、かつて秩父の山々を歩き、未来を信じて「念じて植えよ」と語り続けた本多静六博士の精神が、今も息づいているように思えてなりません。
私たち森林パートナーズも、この精神を受け継ぎ、次の百年へとつながる森林の再生と循環を、地域内の連携によって実現してまいります。私たちが築くのは、「念じて植える」だけではなく、「念じて伐る・加工する・活用する」という連続したサプライチェーンです。
本稿をまとめる中で、あらためて心に残ったのが、本多静六博士の以下の言葉です。
『いつの世にも、根本的な重大問題は山積している。個人の力ではどうにもならぬ難関が立ちはだかっている。しかしながら、各人各個の心掛け次第で、それも順次に取り崩していけぬものでもない。「心掛ける」といった小さな力も、一人の心掛けが十人の心掛けになり、十人の心掛けが百人の心掛けになれば、やがては、千人、万人の大きな力ともなる。百万人の心掛けは百万人の力であり、千万人の心掛けは千万人の力である。
いかにままならぬ世の中と申しても、百万人の力、千万人の力で、これを少しでもままなるほうへもっていけぬということはあるまい。必ずもっていける。必ずよりよき変化は期待し得られる。私はさよう信じてうたがわない。』
(『私の生活流儀』より)
この言葉を読んだとき、自然と今上天皇が皇太子時代に詠まれた御製が心に浮かびました。
岩かげにしたたり落つる山の水大河となり野を流れゆく
一人ひとりの行いが、大きな流れとなって社会を変えていく。天皇陛下の祈りと本多博士の精神を胸に、私たちも秩父の地から行動を続けてまいります。
参考文献:北康利著「本多静六 若者よ、人生に投資せよ」
☆まとめ 「塾頭の一言」酒井秀夫
全国植樹祭は第75回を迎えますが、その積み重ねとは裏腹に、日本の林業は悪循環に陥っています。しかし、国民的行事として、その意義や役割をかみしめながら、これからも継続していきたいです。
埼玉県には、本多静六博士奨学金があります。本多博士が秩父市(旧大滝村)の中津川地域に所有していた森林を県に寄贈されたのが財源になっています。戦後のインフレに対して、森林を持っていたことが強みになりました。秩父の森林は、明治新政府になって税金が金納になったとき、現金で支払えずに他人の所有になってしまった農民の森林を本多博士が買い戻していったものです。その資金は、給料の四分の一を貯金して蓄財したものです。蓄財は0からの出発です。まさに積小為大です。
この奨学金で多くの人材が育ったことと思います。渡部昇一さんもその一人です(『財運はこうしてつかめ 明治の億万長者本多静六開運と蓄財の秘術』)。渡部さんは奨学金によって進学を果たすことができ、思想形成につながっていきました。奨学金を通じて、若い人の心も育んでいたといえます。
本多博士の生地、菖蒲町(現在久喜市)は、関東平野のど真ん中で周囲に山は見えません。なぜ東京山林学校に入学したかというと、学費が安かったからです。森林の中で育ったわけでもない本多博士が植樹祭を提唱したのもおもしろいですが、博士は日本各地に足を伸ばし、『日本森林植物帯論』で学位を取得し、国が敗戦して荒れ果てた森林のこれからの重要性をからだで感じ取っていたからだと思います。一念岩をも通すで、植樹を通して、本多博士の精神に思いを馳せていただければと思います。