□ 椎野潤ブログ(大隅研究会第七回) 「再造林の重要性」
おおすみ百年の森 理事
亀甲 陽海
植林されたスギ・ヒノキ人工林が本格的な利用期を迎え、生産形態が間伐生産から皆伐生産へと変化し、生産工程も架線集材から高性能林業機械を用いた路網集材が主流となってきました。皆伐生産が増えた結果、産量が増加。木材の需要と供給のバランスが心配されましたが、バイオマス発電所用素材及び志布志港からの輸出材といった新たな需要ができ、林業界に明るい光が一気に高まりました。それまで疲弊していた林業界も林業機械に設備投資を行い、生産コスト削減に努めてきたところです。
当初は、活気ある林業界に戻ってきたと思っていましたが、ここ数年、山林(民有林)に変化が出てきました。それが皆伐生産後の再造林がなされない山林が増加していることです。この形態が続くと将来、森林破壊が起こるのではと危惧しています。自然災害が頻発している時代、森林が持つ多面的機能を発揮する為にも再造林が必要です。
しかしながら再造林を行う為には、山林所有者のご理解・再造林コスト(下刈も含)・植栽苗木及び人出不足等いろいろ問題を抱えています。この現状を打破する為にも、川上・川中・川下がお互いに共有し、森林行政のご協力をいただきながら「伐って・植えて・育てる」循環型施業を行い、未来の森作りを行なっていかなければならないと思います。
☆まとめ 「塾頭の一言」 酒井秀夫
森林は誰のものか。もちろん所有者はおられますが、先人からの預かり物で、未来の子孫のものです。経済活動をしながら、確実につないでいかなければなりません。再造林がなされないということは、将来伐る木がなくなるということでもあります。ツケや恩恵が何年もしてから現れてくるのが林業の恐ろしいところです。皆伐生産後の再造林がなされない理由として、日本が置かれている社会や経済状況の中で、コスト、苗木の不足、人手不足、シカの食害等いろいろあると思いますが、森林の衰えは国の衰えです。再造林できる仕組みを整えることは、重要政策課題です。
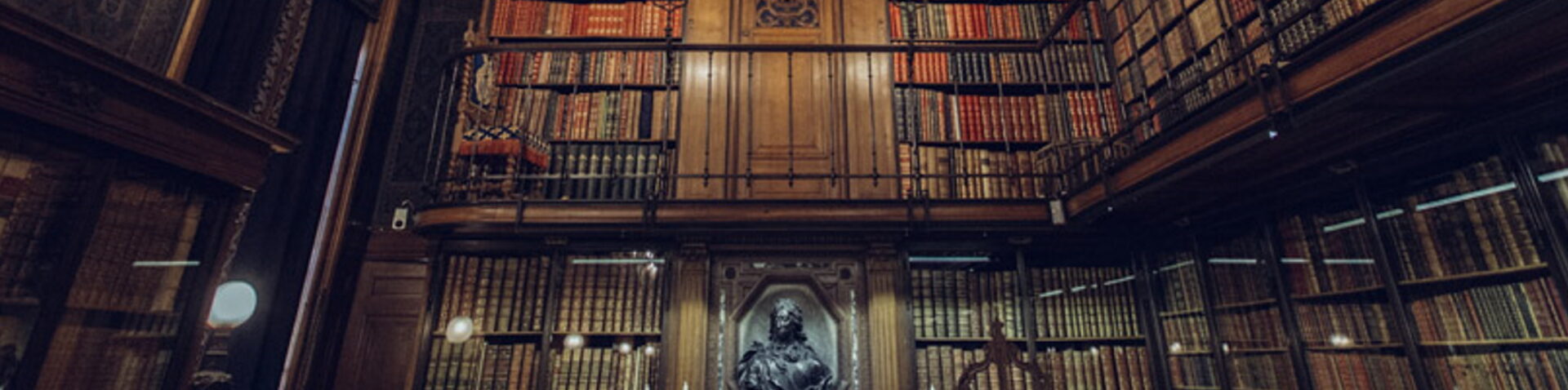

たしかに「森林はだれのモノか」です。
私は森林約800haを所有する財産区議会の議長をしてます。議員就任から間もなく20年に成ります。
就任当初は51歳でした、就任時に財産区財政計画を見て驚きましたが財産区基金3億円の20年後の未来がほぼゼロ価値に想定されてました。 いわゆる財産区を資産として観るのではなく負債として観ていた財政計画でした。 本来の財産区とは財産区を所有している方々に財産区資本を活用して配当するために有る筈だと思って議員に成っていた私からすれば驚愕の未来像でした。
こんな姿に森林が観えるに至った要因はたくさん有るでしょうが、基本は所有者自身が付加価値の創造をする仕掛けになって無かった事だと確信して色んな公的事業を使って財産区基金の積み上げを図って来ました。すべての森林所有者にこの様な思考で森林経営が為されていればと思いますが、相続で棚ぼた式に降り落ちて来る資産を活かせなかった森林所有者の大半が現状の危機的な状態に結果として導いてしまったのでは無いでしょうか?
同時に、森林所有者の組合、森林組合法も造り方がもっと長期的示唆に富む法律であったならばこの様な事態は軽減できたとおもってます。 立場によって異論があるでしょうが45年間森林林業関係に仕えてきた身としての実感です。
吉村様
貴重なコメントに長い事返信せず、本当に申し訳ありません。
今回、一つずつお返しさせて頂きます。
長年、森林林業に関わり、財産区議会の議長もされてこられたとのこと、誠にお疲れ様です。
森林を所有しているのは少なくとも250万戸、地域によっても事情は大きく異なるようです。
ここまでひどい状態になってしまった理由は様々かと思いますが、
問題はこれからどうしていくかですよね。
森林組合法は、やる気になれば実際にはできない事はほぼ無いと聞きます。
佐伯広域森林組合のように、枠を超えて成長し続ける組合もあります。
森林組合がダメならそれに代わる組織が(西粟倉の百森のような)
地域の森林を守りぬいていくための手立てを探っていきたいと思います。