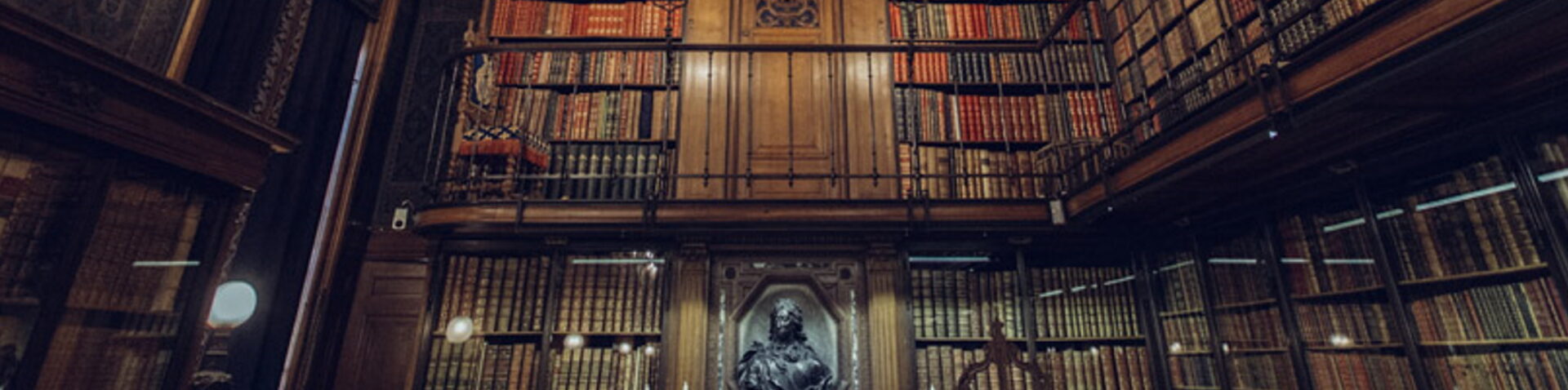□ 椎野潤ブログ(塩地研究会第51回) 地域産業と森林資源の適切で持続可能な関係性(バランス)の構築①
合同会社木人舎代表社員 椎葉博紀
皆様、ご無沙汰しております。前回「再造林のデジタル化で持続性のある生業を地方から興す」と題した投稿から早いもので1年が経ちました。
その間、一次産業者としての関心毎が続いております。
大船渡市において平成以降最大の山林火災が発生しました。被害に遭われ日常生活が一変した多くの皆様にお見舞いを申し上げる次第です。
住まいや生業の拠点に影響が出ておられる方の早期再建が第一であることは勿論ですが、森林(もり)づくりに関わる端くれの一人として、焼失した2,900ヘクタールに及ぶ森林の行く末を案じます。仮に今後、再造林が5割としても1,500ヘクタール。僅かな日数で焼失した森をどのように再生させていくのか?人手は有るのか?山行苗は有るのか?森林という国土をどう守り抜いていくのか?人為と天為を高度に組み合わせた復興森づくりについて、関心深く推移を見守りたいと思います。
国外に目をやると、カナダで発生している(執筆時点)山林火災では200万ヘクタールを超える森林焼失面積とか。報道では東京ドーム43万個分と表現されますが、規模感が伝わりません。沖縄を除く九州各県の森林面積合計が約266万ヘクタール(鹿児島59万、宮崎59万、熊本46万、大分45万、長崎24万、福岡22万、佐賀11万)ですので、鹿児島もしくは宮崎と佐賀を除く九州の森林が焼失したと考えてみますと・・・あまりの規模に恐怖すら覚えます。
そして、昨今のコメ騒動。ここで多くを述べることは控えますが、私が身を置く業界にも置き換えることが出来る課題が見え隠れするように感じます。
私が暮らす地域に目をやりますと、令和2年7月に球磨川流域を襲った大水害から5年を迎えます。街中が茶一色のモノクロな世界に覆われ、尊い犠牲と甚大な損害を被った過去の上に今の営みがあります。
発災して間もなく、当時市職員であった私は、被災者向け住宅支援部署へ異動となり仮設住宅の整備にも携わっておりました。その後間もなくして、復興まちづくりの計画担当へ異動となりトップスピードで走り抜けていた日々を思い出します。
当時の役目を投げ出し、市職員としての区切りをつけて森林セクターに移るという判断に葛藤がなかったわけではありません。自問自答の毎日であったのは間違いありませんが、その当時の葛藤が今の行動原則(原因療法実践者の一人になる)に繋がっています。
前回ブログ記事からの1年をもう少し振り返ります。自身の視座を広げるいくつもの出来事に恵まれました。正に、「百聞は一見に如かず」の連続でした。
鹿児島大学において森林と建築が接合していくきっかけに触れました。
佐伯・耳川の再造林ツアーでは、九州の近接する地域にあっても森林・林業との向き合い方はこうも違うのかということを目にし、改めて、林業は他者への思いやりで成り立つことに触れました。
福岡・千葉の大型パネル工場視察等では、在来軸組完全自由設計下での大型パネル工法とは何ぞやを学び、自身の誤解を解き、そして、超えるべき新たなハードルを見つける機会になりました。
もう少々、リアルタイムでの課題認識を続けます。
これから森林や林業に向き合っていきたいという方向けの研修において講師役を務めた時の一幕、その時いただいた質問が今も強烈に頭に残ります。
『「多かった時期に比べ担い手が激減し、林業の担い手が不足しています!手入れが遅れ森林は危機に瀕しています!」そのようなお決まりのセリフは数多聞く。では一体、日本全体で何人の担い手がいればよいのか?あと何人必要なのか?』と。。。
鋭い質問です。私は答えに窮しました。
『林業従事者が多かった時と比べると大幅な減少になっているのは統計的な数字が出ていますから・・・少なくとも担い手が不足しているのは間違いないのでしょうが・・・あと何人必要です、とは申し上げることができません。』としか答えることができませんでした。
国内の森林面積、人工林面積、森林蓄積など、ボリュームの大枠は概ね把握ができます。技術の進歩なども踏まえると、過去と現在の単純な比較も大きな意味を持たないようにも感じます。
もしかすると、今くらいが適切なのか?
森林を始めとした自然由来の生業に関連する者は、増えすぎても減りすぎてもいけない適正規模があるのではないか?技術進歩や需要動向などの与条件を踏まえると適正といえる事業規模があるのではないか?
それすら見えていない状況で得意げに講話をする自分が恥ずかしくなりました。
次回は、日常業務で感じる手応えと、一方で到底追いつかない、森林・林業の抱える課題の大きさ、その間で自分の役割をどう整理していくのかについて書きたいと思います。
☆まとめ 「塾頭の一言」 酒井秀夫
球磨川大水害を市職員として復興という激職に携わった経験をお持ちで、原因療法実践が行動原則の椎葉さんの寄稿です。
自然災害が多発していますが、復興の資材として、苗木ひとつとっても、常に多めにつくって備えておかなければなりません。幸いにして災害がなかった場合、不要になった苗は廃苗しなければなりません。さりとて、備えていないといざというとき、途方に暮れるだけです。
前々回6月16日のテーマは、「森林は誰のもの?」でしたが、今回登場する研修生の質問は、煎じ詰めれば「何を目的にした誰のための林業?」になると思います。林業も社会が変われば変わっていきます。いまある人工林は、林業従事者が30万人以上おられた頃に造成されたものです。途中から間伐放棄の林分も出てきました。今の林業従事者数で往時と同じことはできません。30年前の1990年、国産材供給量は2,937万㎥で林業従事者は11万人でしたから、労働生産性は単純に計算すると267㎥/人年です。令和2年の国産材供給量は3,090万㎥で、林業従事者は4.4万人でしたから、労働生産性は702㎥/人年です。木も大きく育って施業の内容が変わってきたり、機械化が進んだりしたこともあって、数字の上での労働生産性は大きく向上しています。しかし、将来4,000万m3を目指し、林業従事者が3万人にまで減ったとすると、労働生産性は1,333m3/人年にまで増やさなければなりません。林業従事者を増やすか、生産性の技術革新をしなければなりません。
林業に限らず、社会は海外も含めて大きく変わろうとしています。目の前にあるようやくここまで育ててきた森林をこれからどうしていくか?後世の人が冷徹な眼で問いかけてきています。